

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
保有資格
AFP・2級FP技能士
専門分野・得意分野
生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。
死亡保険金を受け取るとき、「税金がかかるのか、かからないのか」は誰もが気になるポイントです。
本記事では、死亡保険金にかかる相続税・所得税・贈与税の違いや、税金面で損をしないための契約形態をプロがわかりやすく解説し、家計や老後資金への影響を減らせる知識を提供します。
どんな場合に死亡保険金に税金がかかる?契約形態別に整理
死亡保険金がどの税金の対象になるかは、契約者・被保険者・受取人の関係で異なります。
相続税・所得税・贈与税のそれぞれについてケースごとに説明します。
1. 相続税がかかるケース
契約者・被保険者が同一で、受取人が法定相続人の場合は相続税が適用されます。
非課税枠「500万円×法定相続人の数」を超えた部分が課税対象です。
2. 所得税がかかるケース
契約者と受取人が同一で、被保険者が別人の場合、所得税(一時所得)が適用されます。
差額から50万円控除し、さらに1/2にした金額が課税対象になります。
3. 贈与税がかかるケース
契約者・被保険者・受取人がすべて異なる場合には贈与税が課されます。
110万円を超える部分に贈与税率が適用されます。
4. 税金がかからないケース
非課税枠内に収まっている場合や、配偶者への税額軽減制度が活用される場合は税金がかからないこともあります。
保有財産との合算に注意が必要です。
5. 損を防ぐ契約形態の工夫
契約者=被保険者=本人、受取人=配偶者・子の形にすることで相続税の非課税枠を最大限に活用できます。
税制優遇を受けられる最もおすすめの契約スタイルです。
相続税がかからないケースは?非課税限度額の活用
死亡保険金に対する非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で、これを超えなければ相続税はかかりません。
養子の数や相続人の扱いによる注意点も具体的に押さえておきましょう。
所得税(一時所得)に課税されるケースとは?計算例付き
契約者と受取人が同じ場合、死亡保険金は所得税(一時所得)の対象になります。
支払った保険料や控除額の差し引き後の計算方法も具体例で解説します。
贈与税がかかるケースとその税額の目安
被保険者と契約者・受取人が異なる場合など、贈与税がかかることもあります。
基礎控除や税率を踏まえた具体的な税金額のシミュレーションも示します。
ポイント解説
契約形態によって「相続税」「所得税」「贈与税」のどれが適用されるか変わります。非課税枠や控除を賢く使いましょう。
税額シミュレーションの具体例
実際の金額を使い、以下のような家族構成で計算例を示します:
・本人・配偶者・子2人の家庭で、4000万円の保険金を受け取った場合、相続税はかかるのか?
死亡保険金を受け取った後の申告期限をチェック!
所得税・相続税・贈与税ではそれぞれ申告期限が異なります。
期限を過ぎると延滞税や加算税が課される可能性があるため、早めの対応が重要です。
FPに聞く!死亡保険金と税のリアルな疑問

実際の相談現場でよくある質問をFPがわかりやすく回答します。
34歳・女性
死亡保険金には非課税枠があると聞きました。どんな相続人が対象ですか?
スマホdeほけん
非課税枠「500万円×法定相続人の数」の対象は戸籍上の配偶者および2親等以内の血族です。養子の人数制限にも注意しましょう。
34歳・女性
契約者と受取人が同じ場合、どう税金がかかりますか?
スマホdeほけん
所得税(一時所得)の対象になります。「受取額-支払保険料-50万円(特別控除)」の1/2が課税対象額です。
34歳・女性
贈与税がかかるケースはどんなとき?
スマホdeほけん
契約者と被保険者・受取人が異なると、贈与税の対象になります。基礎控除110万円を超えると課税対象です。
34歳・女性
申告期限を過ぎるとどうなりますか?
スマホdeほけん
所得税は翌年2月16日〜3月15日、相続税は10ヶ月以内、贈与税は翌年2月1日〜3月15日です。遅れると加算税や延滞税が生じることがあります。
Q&A:よくある質問に回答

Q1. 非課税限度額を超えたらどうなる?
A. 超えた部分は相続税の対象になります。その際には相続税の控除や配偶者の税額軽減も考慮されます。
Q2. 法定外の受取人にした場合、どうなる?
A. 非課税限度額が適用されず、贈与税や所得税が高くなる可能性があります。慎重に検討することが重要です。
Q3. 所得税の計算で支払った保険料はどう扱われますか?
A. 実際に支払った保険料が差し引き対象となり、特別控除の50万円とともに一時所得の課税額を計算します。
Q4. 複数の死亡保険に加入している場合は?
A. 全ての契約を合算して非課税枠や控除を計算する必要があります。一つずつ計算するのではなく合計額で判断されます。
Q5. 税理士やFPに相談すべきポイントは?
A. 計算の正確性の確認、申告期限の管理、そして節税に有利な契約形態の提案などを相談することが有効です。
まとめ
死亡保険金にかかる税金は、契約形態と受取人との関係から異なります。
「相続税の非課税枠」「所得税の控除」「贈与税の基礎控除」を活かすことで、家計や資産形成の観点からも有利にできます。
不安がある場合は、早めに専門家へ相談し、安心できる契約設計をおすすめします。
公的制度・公式リンク集
死亡保険金と税金については、公的機関の公式サイトで最新情報を確認しましょう。
| サイト名 | 内容 |
|---|---|
| 国税庁 | 死亡保険金の課税関係(相続税・所得税・贈与税) |
| 国税庁|相続税の申告手続き | 相続税の申告期限・方法 |
| 国税庁|所得税・贈与税の申告手続き | 申告期限・必要書類の案内 |
| 日本FP協会 | 家計・保険に関するFPの無料相談 |
| 法テラス(日本司法支援センター) | 法的相談(遺産相続や契約の不明点) |
監修者からひとこと




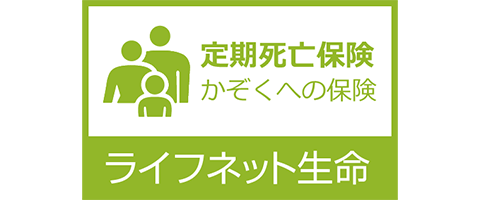
スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
本記事では、死亡保険金にかかる税金について、契約形態や受取人との関係性を整理しました。
「相続税」「所得税」「贈与税」の違い、非課税枠の活用、申告期限の注意点を押さえることで、家計への負担を最小限にできる提案を目指しています。必要であればFPや税理士への相談も検討しましょう。