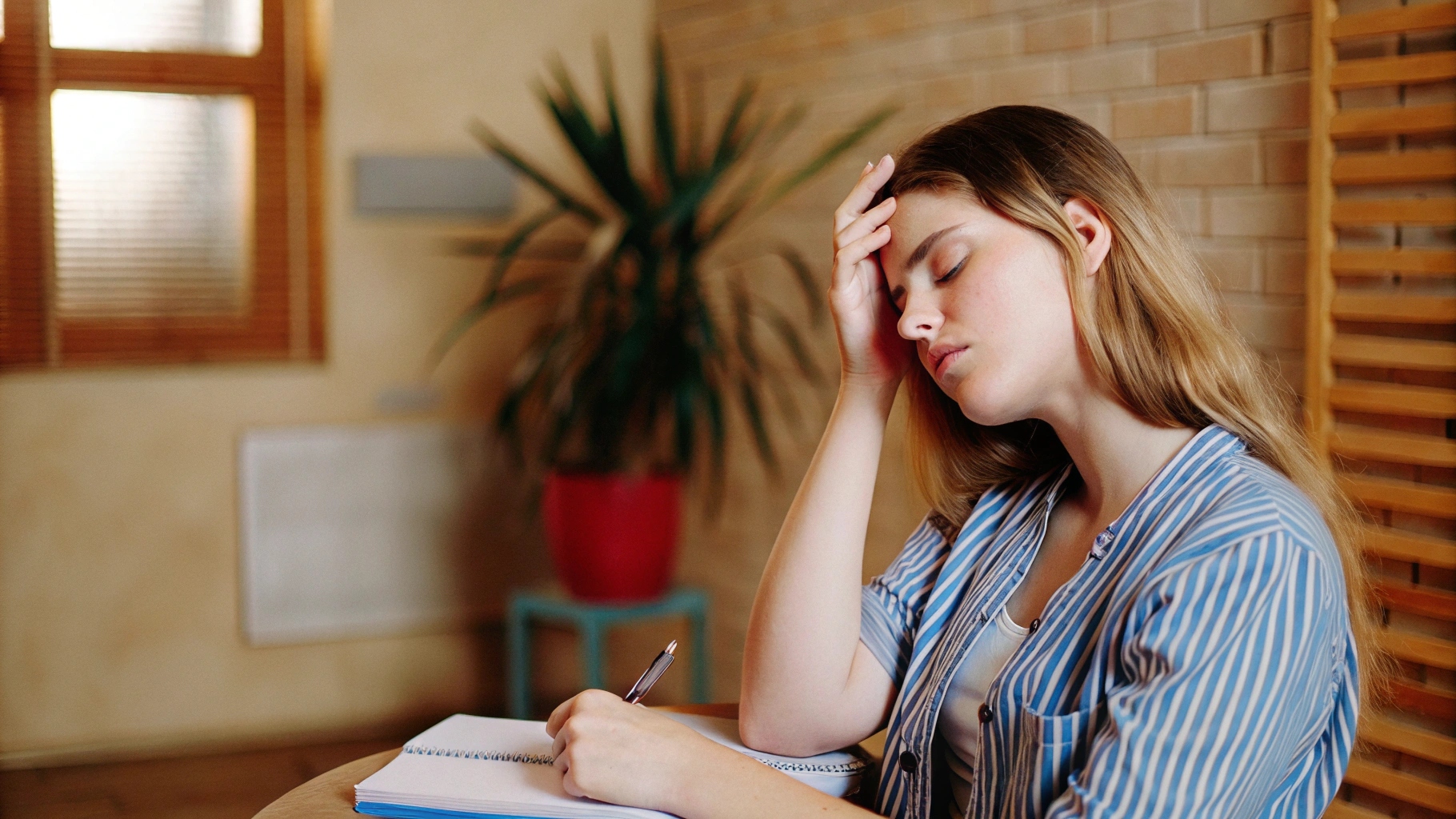

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
保有資格
AFP・2級FP技能士
専門分野・得意分野
生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。
パニック障害は、入院や手術を伴わないことが多く、医療保険の給付対象外となるケースが一般的です。
しかし、将来的な疾病や合併症に備える意味でも、引受基準緩和型医療保険という選択肢が注目されています。この記事では、パニック障害の治療実態と保険加入の現実的な選択肢を解説します。
パニック障害とは?症状と治療、生活への影響
パニック障害は、突発的な強い不安や身体症状(動悸、発汗、息切れなど)を繰り返す精神疾患です。原因はストレスや脳内の神経伝達物質の乱れとされます。
治療は抗うつ薬や抗不安薬による薬物療法と、認知行動療法などの精神療法が中心で、長期間にわたる通院治療が必要になることが一般的です。
医療保険では給付対象外?その理由と実情
パニック障害は、入院や手術を行わない場合が多く、通常の医療保険では給付対象外になることがほとんどです。
また、通院給付金についても、精神疾患が支給対象外と明記されている保険商品が多く、実際の治療費を補填するのは難しい状況です。
| 特徴 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 一般医療保険 | 幅広い疾病に対応 | 精神疾患は給付対象外が多い |
| 引受基準緩和型医療保険 | 過去の病歴があっても加入しやすい | 保障範囲が限定される |
| 無選択型医療保険 | 告知不要で加入できる | 加入後一定期間は保障制限あり |
引受緩和型医療保険とは?パニック障害でも加入できる可能性
引受基準緩和型医療保険は、一般の医療保険と比べて告知内容が簡略化されており、病歴がある人でも加入しやすい医療保険です。
ただし、告知項目をすべて「いいえ」で答えられることが加入の条件となるため、現状の通院や服薬の有無がポイントになります。
1. 加入可能な保険の種類を知る
パニック障害があっても、引受基準緩和型医療保険や無選択型医療保険であれば加入できる可能性があります。
ただし、給付対象が限定されるため、目的に合った内容を確認しましょう。
2. 告知項目の内容とチェック
引受基準緩和型医療保険の代表的な告知項目は以下の通りです:
・最近3か月以内に医師の診察・治療・投薬を受けたか
・過去2年以内に入院または手術を受けたか
・過去5年以内に重い病気(がん・肝硬変・腎不全など)で入院・手術歴があるか
これらに「すべて該当しない」と答えられれば、加入が可能となります。
3. 治療中かどうかが分かれ道
現在もパニック障害で通院・服薬中であれば「告知あり」となり、加入できない可能性があります。
一方、完治後や服薬終了後で一定期間が経過していれば、加入できる可能性が高くなります。
注意ポイント
同じ病歴でも、保険会社ごとに加入可否は異なります。事前に資料を取り寄せて比較することが大切です。
4. 保障範囲と保険料のバランス
緩和型保険は保障内容が限定される一方、保険料が割高になる傾向があります。
自分が何に備えたいのかを明確にし、無理のない保険料で必要な保障を得られるか見極めましょう。
5. 公的制度との併用
精神疾患の治療には「自立支援医療制度」を活用すると、通院医療費の自己負担を原則1割に軽減できます。
医療保険だけでなく、こうした制度を併用することで経済的負担を抑えることが可能です。
Q&A|パニック障害と医療保険に関するよくある質問
Q1. パニック障害でも保険に加入できますか?
A. 通常の医療保険は難しいですが、引受緩和型医療保険であれば条件付きで加入できる可能性があります。
Q2. 通院中でも加入できる保険はありますか?
A. 多くの緩和型保険は通院中だと加入できません。治療終了後に一定期間が経過していることが条件です。
Q3. 精神疾患が給付対象となる医療保険はありますか?
A. 一部に該当する商品もありますが、非常に限定的です。加入前に保障範囲を必ず確認しましょう。
Q4. 公的な支援は受けられますか?
A. はい。自立支援医療制度を利用すれば、精神科通院の医療費負担が軽減されます。
Q5. パニック障害が治っていれば保険加入のチャンスはありますか?
A. はい。通院・投薬終了後に一定期間経過していれば、加入できる商品もあります。
まとめ|パニック障害でも将来に備えるなら「今」が判断の分かれ道
パニック障害は給付対象外が多い疾患ですが、保険に全く入れないわけではありません。
引受緩和型医療保険など、条件付きでも加入できる選択肢を検討し、将来のための備えを整えましょう。
監修者からひとこと


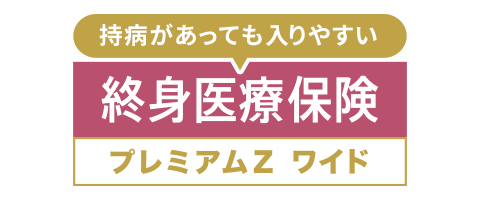

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
パニック障害のような精神疾患は、一般的な医療保険の対象外となることが多く、知らずに加入しても給付を受けられないリスクがあります。
だからこそ、今の健康状態を正しく把握し、加入可能な保険の選択肢を早めに検討しておくことが将来の安心につながります。