

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
保有資格
AFP・2級FP技能士
専門分野・得意分野
生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。
「子どもが起立性調節障害と診断されたけれど、保険に加入できるの?」「体調の波があって将来が不安…」という保護者の方も多いのではないでしょうか。
起立性調節障害は自律神経系の不調によって朝起きられない、ふらつきや失神を伴う疾患であり、継続的な通院や治療が必要となるケースもあります。医療費や将来の保障を考えるうえで、適切な保険選びはとても重要です。
起立性調節障害と医療保険|通常加入は難しいがチャンスはある
起立性調節障害は「慢性疾患」として扱われるため、通常の医療保険では加入が難しいことが多いです。
特に診断後3年以内や通院治療中の場合、審査で加入を断られるケースも少なくありません。しかし、引受基準緩和型医療保険であれば、告知が簡易化され、加入できる可能性が高まります。
引受基準緩和型保険なら加入しやすい!5つの確認ポイント
引受基準緩和型医療保険は、通常の保険と異なり、過去の病歴があっても入りやすい設計になっています。
ただし、商品によっては起立性調節障害に関する給付制限や待機期間が設けられているため、契約前に必ず確認が必要です。
加入前に確認したい5つのポイント
1. 告知項目が簡略化されている
引受緩和型では「過去2年以内の入院や手術」「3カ月以内の通院や薬の使用」などに限られています。
起立性調節障害の治療状況によっては、告知対象外となり加入可能な場合もあります。
2. 精神・神経疾患への給付範囲
一部の保険商品では、自律神経失調症などと同様に、神経疾患由来の入院・通院が給付対象外となることがあります。
保障内容を丁寧に確認し、対象かどうかを判断する必要があります。
3. 発症前治療への免責規定
加入前から通院していた場合、一定期間給付対象外となる「免責期間」が設けられているケースもあります。
契約から3カ月以内の入院や手術は対象外となることが多いため注意しましょう。
4. 保険料と保障バランス
引受緩和型は通常の医療保険よりも保険料が高めですが、持病があっても加入できるという安心があります。
保険料だけでなく、給付金額や通院保障の有無も確認して、自分に合ったバランスを選びましょう。
5. 保障内容の比較検討
保険会社によって精神・神経疾患の定義や免責内容が異なるため、最低でも2~3社は比較検討を行うことが理想です。
保障対象の範囲や給付制限の有無をしっかり確認しましょう。
起立性調節障害で使える公的支援制度も要チェック
起立性調節障害による通院・治療の経済的負担を軽減するために、公的制度の活用も有効です。
特に次のような支援は、家計の助けになります。
| 制度名 | 内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| 小児慢性特定疾病医療費助成 | 医療費の自己負担を軽減 | 指定された慢性疾患の児童 |
| 高額療養費制度 | 医療費が一定額を超えた際に支給 | 保険適用治療の受診者 |
| 医療費控除 | 年間医療費が一定額を超えた場合に所得控除 | 納税者本人または家族 |
Q&A|起立性調節障害と医療保険の気になる疑問
Q1. 起立性調節障害があっても医療保険に加入できますか?
A. 通常の医療保険では難しい場合もありますが、引受基準緩和型保険なら加入できる可能性があります。
Q2. 起立性調節障害による通院でも給付は受けられますか?
A. 保険会社によっては精神・神経疾患の通院給付を除外していることもあります。保障内容をよく確認しましょう。
Q3. 保険加入時の告知にはどこまで記載が必要ですか?
A. 過去の診断・治療・服薬歴が告知対象になります。虚偽の申告は契約無効のリスクがあるため正確に記入しましょう。
Q4. 保険料は通常より高いですか?
A. はい、引受緩和型は割高になりますが、加入ハードルが低いため、治療中でも安心の保障を得られます。
Q5. 成長して症状が改善したら保険を見直すべきですか?
A. 状況が改善した後は、通常の医療保険への切り替えを検討してもよいでしょう。見直しは定期的に行いましょう。
まとめ|起立性調節障害でも医療保険で将来に備えられる
起立性調節障害がある場合、通常の医療保険には加入しづらいものの、引受基準緩和型医療保険であれば加入できる可能性があります。
保障範囲や免責条件を丁寧に確認し、自分にとって最適な保険を選ぶことで、長期的な治療にも安心して備えることができます。
監修者からひとこと


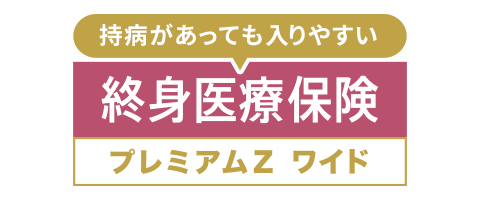

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
起立性調節障害は成長期に多く見られ、症状も幅広く個人差があります。医療費の支援を受けながら、無理なく保障を整えることが大切です。
引受緩和型保険は、通常の医療保険に加入しづらい方にとって有力な選択肢です。内容を理解し、自分に合ったプランを見極めることが、治療と生活の両面において安心をもたらす鍵となります。