

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
保有資格
AFP・2級FP技能士
専門分野・得意分野
生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。
「通院歴がバレたら入れない?」と不安な方へ。結論、条件付きや商品選択で加入の道はあります。
家計と老後資金を守る視点で、告知のコツ、入りやすい保険タイプ、避けたいNGまでをやさしく解説します。
結論と全体像|通院歴があっても“設計次第”で加入余地あり
最終通院からの経過年数、完治証明、入院歴の有無で選べる保険が変わります。通常の医療保険や死亡保険での条件付き加入、引受基準緩和型、無選択型が現実的な選択肢です。
まずは必要保障額と保険料の上限を決め、総支払額で比較しましょう。加入後の見直し時期も決めておくと固定費の暴走を防げます。
1. 5年ルールと完治証明の扱い
多くの会社で「直近5年」の診療・投薬・入院歴が審査の軸です。5年以上経過かつ再診なしなら通常加入の余地が広がります。
5年未満でも医師の所見で寛解・完治の証明があれば前向き判断となることがあります。
2. 通常加入か部位・疾病不担保か
精神・神経領域に限定した不担保や特別条件(割増保険料等)が付くことがあります。期間と解除条件を必ず確認しましょう。
将来解除可なら、更新・節目年で条件緩和の交渉余地があります。
3. 引受基準緩和型・無選択型の使い分け
告知項目が少ない緩和型は加入ハードルを下げますが、保険料は割高・給付制限もあり得ます。無選択は更に入りやすい反面、上限や削減期間に注意。
“つなぎ”として短期採用→状態安定後に通常商品へ乗換える戦略が有効です。
4. 家計影響と必要保障額の算出
入院日額・手術一時金・就業不能のカバーを合算し、貯蓄・公的制度で埋まる分を差し引いて必要額を決めます。
教育費・老後資産形成(変額保険やNISA)とのバランスで月額上限を設定しましょう。
5. 加入後の見直しと請求動線
症状の安定やライフイベントで見直し。請求時はWeb申請・医師証明の要否・支払所要日数も事前に把握しておくと安心です。
窓口のサポート品質も重視し、いざに備える体制を整えます。
注意ポイント
「入りやすさ」だけで選ぶと過剰保障と高コストに。必要給付を最小化し、余力は緊急資金や積立・変額保険で資産形成に回すのが定石です。
通院歴は“なぜ”バレる?|告知義務と調査の実務
給付請求時に診療情報や健診結果の確認が入るため、通院歴は高確率で判明します。虚偽・遺漏は不払い・解除のリスクです。
過去の健診所見・紹介状・服薬履歴を整理し、一貫した告知を心がけましょう。
1. 診療経過と服薬の時系列整理
初診日・最終受診日・薬剤名・中止時期をメモ化。申込書との齟齬を防げます。
手元の記録は給付請求でも役立ちます。
2. 主治医の見解(寛解・完治)の確認
所見が前向きだと審査がスムーズ。診療情報提供書があると説得力が上がります。
追加の精査予定がある場合は条件付き想定で比較検討を。
3. 入院・手術・休職歴の有無
7日以上の入院や長期休職は重要情報。就業不能の備えも合わせて検討します。
収入減少リスクは家計の致命傷になりやすいため優先度は高めです。
4. 加入目的と必要保障額の根拠
目的(入院・手術・就業不能)ごとに必要額を算出。根拠を持てば無駄な特約を外せます。
固定費の最適化で長期の継続性が高まります。
5. 公的制度との役割分担
高額療養費や傷病手当金の適用を前提に、民間保険は不足分をカバー。
制度の自己負担上限・支給条件を理解して設計します。
ここが実務のコツ
申込→成立→見直しのスケジュールを最初に決めておくと、条件緩和や乗換えのタイミングを逃しません。
タイプ別の比較表|通常・緩和・無選択
代表的な保険タイプの違いを俯瞰し、優先順位に合わせて選びましょう。
詳細条件は会社ごとに差があるため、約款と設計書で必ず確認してください。
| 特徴 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 通常の医療・死亡保険 | 保険料が割安で広い保障 | 不担保・特別条件が付く場合あり |
| 引受基準緩和型 | 告知が少なく加入しやすい | 割高・給付制限や待機期間の可能性 |
| 無選択型 | 告知ほぼ不要で加入しやすい | 上限・削減期間が長めでコスパ低下 |
FPに聞く!心療内科と保険・家計のリアル

読者の疑問にFPが簡潔に回答します。家計や就業不能リスクの視点も交えて解説。
34歳・女性
通院歴があっても本当に入れますか?
スマホdeほけん
可能性はあります。通常商品の条件付き、緩和型、無選択型の順で比較し、保険料と保障の釣り合いを見ます。
34歳・女性
告知で注意する点は?
スマホdeほけん
最終受診日や服薬状況、入院・休職歴は正確に。必要なら主治医の所見を添えて整合性を確保します。
34歳・女性
家計の負担を抑えるコツは?
スマホdeほけん
必要給付を最小限にし、残りは緊急資金と長期の資産形成で補います。固定費は年1回見直しましょう。
34歳・女性
就業不能の備えは必要?
スマホdeほけん
重要です。就業不能保険や公的制度と併用し、収入減少への備えを厚くします。
34歳・女性
加入後の乗換えは?
スマホdeほけん
状態安定後に通常商品へ乗換えを検討。更新時や条件解除時期に合わせて計画するとスムーズです。
Q&A|心療内科と生命保険のよくある質問

迷いがちな論点を5つに絞って回答します。最終判断は約款と最新の引受基準で確認しましょう。
不明点は専門家に相談し、個別事情に合わせて調整してください。
Q1. 通院歴のデメリットは?
A. 加入選択肢が狭まり、条件付きや割増保険料になる可能性があります。
ただし経過年数や所見次第で通常加入へ広がるケースもあります。
Q2. 一度だけ受診していても影響しますか?
A. 1回でも告知対象になり得ます。5年以上経過なら影響が軽くなる傾向です。
5年未満は緩和型や無選択型での検討が現実的です。
Q3. なぜ入りにくいのですか?
A. 入院・治療の発生確率が相対的に高いと見なされるためです。
公平性の観点から引受基準で調整されています。
Q4. 心療内科は健康保険の対象?
A. はい、診療・処方の多くは公的医療保険の対象で自己負担3割です。
一部カウンセリング等は自費のことがあるため事前確認を。
Q5. 既契約は通院後も更新できますか?
A. 原則、継続更新は可能です。ただし特約追加や増額時は再告知が必要な場合があります。
更新時は追加契約を急がず、別枠で比較検討しましょう。
まとめ|正しい告知と賢い商品選択で加入の道を拓く
通院歴があっても“加入は可能”。5年経過・完治所見の有無で通常加入や条件付き、緩和型・無選択型を戦略的に選びましょう。
公的制度と役割分担し、就業不能も含めた全体設計で、家計負担を抑えつつ長期の安心を確保します。
監修者からひとこと



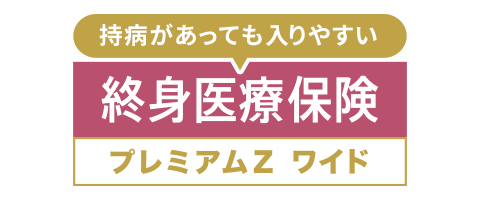

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
心療内科の通院歴はデリケートですが、ポイントは「正確な告知」「約款の但し書き確認」「家計と資産形成の両立」です。入りやすさ優先で高コスト化するより、必要給付を絞り、状態が安定したら通常商品へ段階的に移行する設計が合理的です。
また、就業不能や収入保障の視点を足すと保障の穴が埋まります。年1回の見直しを習慣化し、固定費を最適化しましょう。専門家の横断比較は、時間短縮とミス防止に有効です。