

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
保有資格
AFP・2級FP技能士
専門分野・得意分野
生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。
月経困難症は、生理痛が日常生活に支障をきたすレベルで現れる疾患で、日本人女性の約25%が罹患しているとされています。
とくに20〜30代の女性に多く、通院や薬の処方など治療費がかかることから、医療保険による保障の有無は気になるポイントです。
月経困難症とは?分類と症状の特徴
月経困難症は、大きく機能性(月経に伴うホルモンバランス)と器質性(子宮筋腫など)の2種類に分かれます。
症状は腹痛や腰痛、吐き気、頭痛など多岐にわたり、学校や仕事を休むほど重度になる場合もあります。
医療保険で確認すべきポイント
1. 治療費に対する保障の可否
月経困難症で婦人科を受診した場合、診療や検査、薬代が医療費として発生します。
医療保険で保障を受けるには、契約内容や対象疾患に該当している必要があります。
2. 通院保障の条件
医療保険の中には、入院なしの通院のみでは給付対象とならない商品もあります。
通院特約の付帯や、一定回数以上の通院が条件になることがあるため、事前の確認が大切です。
3. 女性疾病特約の有無
月経困難症は女性特有の疾患として、女性疾病特約が適用される保険もあります。
この特約により、通院・入院・手術などに対する給付が手厚くなる場合があります。
4. ピル使用時の告知義務
低用量ピルなどの薬剤を使用している場合、保険加入時に告知義務が生じることがあります。
治療目的か避妊目的かによって扱いが変わるため、正確な申告が必要です。
5. 保障の対象外になるケース
軽度な生理痛や、市販薬での自己管理レベルでは給付対象とならないケースが多いです。
医師の診断書や診療明細など、正式な治療記録があるかどうかがポイントになります。
医学的視点から見た月経困難症の対処法
月経困難症は、女性ホルモンの変動によるプロスタグランジン過剰分泌が主因とされます。
鎮痛剤やLEP(低用量エストロゲン・プロゲスチン配合薬)によるホルモン調整が有効とされており、保険診療での治療が可能です。
治療継続の重要性
月経困難症は放置すると子宮内膜症などを引き起こす可能性があります。定期的な診療と継続治療が将来の健康を守ります。
Q&A:月経困難症と医療保険のよくある疑問
Q1. 月経困難症は医療保険で保障されますか?
A. 保険契約内容により異なりますが、女性疾病特約を付加していれば保障対象となるケースが多いです。
Q2. ピルを服用中でも保険に加入できますか?
A. 治療目的で服用していれば加入可能なことが多いですが、告知が必要です。
Q3. 学生でも医療保険に入った方がよい?
A. はい。月経困難症は10代後半から発症しやすいため、早期加入がおすすめです。
Q4. 自費治療は保障されますか?
A. 保険診療が対象のため、自費治療分は給付対象外となります。
Q5. 治療歴があると加入できませんか?
A. 軽度な経過であれば加入可能なケースもあります。保険会社による審査が必要です。
まとめ
月経困難症は、月経のたびに強い腹痛や腰痛、吐き気、頭痛などの症状が現れ、日常生活や仕事に支障をきたすことも多い疾患です。特に若年層の女性に多く見られ、放置すると子宮内膜症などの病気が隠れている場合もあるため、早期の受診と継続的な治療が重要とされています。
治療には鎮痛薬やホルモン療法、低用量ピルなどが用いられますが、長期的な通院や薬の服用が必要になるケースも少なくありません。そのため、医療費の負担が継続的に発生し、経済的なストレスを感じる方も多いのが実情です。
このような状況に備える手段として、女性疾病特約や通院保障を付帯した医療保険の活用が有効です。女性疾病特約では、月経困難症をはじめとした女性特有の病気に対する給付金が手厚く設定されていることが多く、治療継続の心理的・経済的な支えとなります。また、通院保障があれば定期的な診察や処方薬にかかる費用を補うことができ、負担の軽減につながります。
月経困難症は「我慢すればよいもの」と考えられがちですが、適切な医療的対処を行うことで症状の改善が期待できます。日々の生活の質を守るためにも、自分に合った保険でしっかりと備えることが大切です。
監修者からひとこと




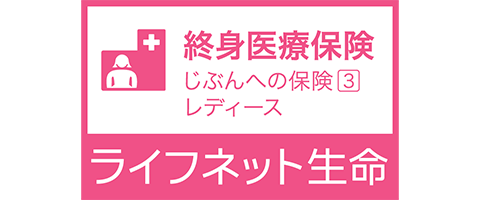
スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
月経困難症は医療機関での治療が必要なケースも多く、放置すべきではありません。
医療保険を正しく理解し、ライフステージに合わせた保障を選択することが将来の安心につながります。