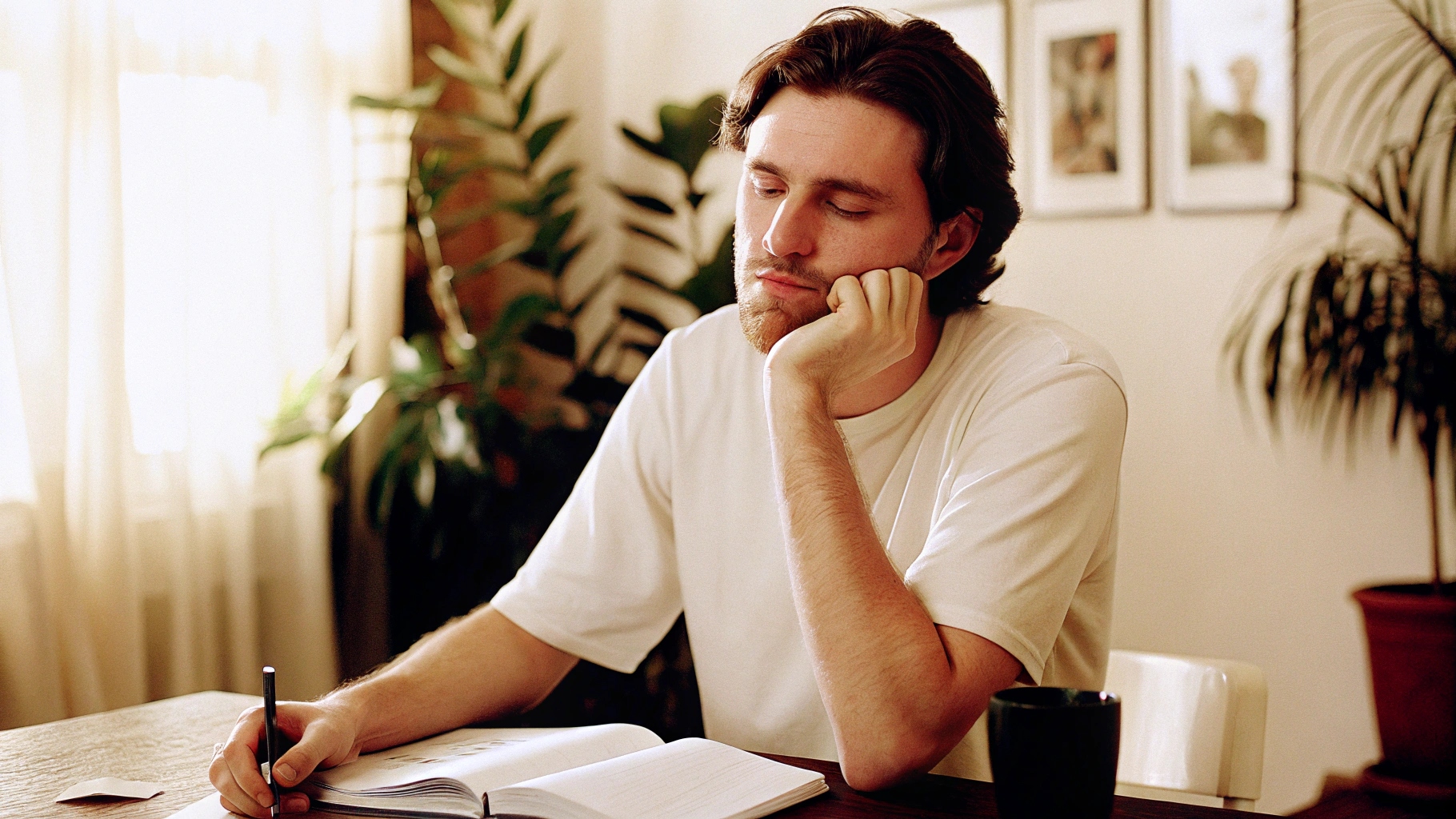

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
保有資格
AFP・2級FP技能士
専門分野・得意分野
生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。
「医療保険って、本当に必要なの?」と疑問に思ったことがある方は多いのではないでしょうか。
実際、ネット上では「医療保険は無駄」「入らなくていい」という意見も多く見られます。
一方で、病気やケガによって医療費がかさみ、「加入しておけばよかった」と後悔した事例も存在します。
この記事では、医療保険が「いらない」とされる理由を冷静に分析し、必要な人の特徴や判断基準を専門家の視点で詳しく解説します。
医療保険が「いらない」と言われる5つの理由
医療保険が「不要」とされる背景には、合理的な根拠が存在します。
代表的な5つの理由を見てみましょう。
医療保険が不要とされる理由
1. 公的医療制度が充実している
高額療養費制度や健康保険によって、自己負担額が一定水準に抑えられます。
制度を理解して活用することで、保険に頼らなくても対応できるケースがあります。
2. 入院日数が短縮傾向にある
厚生労働省の統計によると、入院の平均日数は年々短くなっています。
軽度の入院であれば、大きな出費にならない場合もあります。
3. 預貯金でまかなえる
貯金がしっかりある方にとっては、軽い病気や短期入院は自己負担可能です。
「貯蓄=保険」と考える方も少なくありません。
4. 給付条件が複雑
特約の内容や給付の条件がわかりにくく、理解しにくい保険商品も多くあります。
不明点が多いと、加入への心理的ハードルが上がります。
5. 長期間で支払額が増える
月々数千円の保険料でも、20年・30年と払えば数十万円〜百万円規模になります。
費用対効果を重視する人ほど慎重になる傾向があります。
医療保険に入らず後悔した人のリアルな声
「医療保険はいらない」と判断して未加入のまま、後悔した人の事例を紹介します。
実際の声から学ぶことが多く、判断材料として非常に参考になります。
1. 30代・会社員男性の盲腸入院
急な盲腸手術で5日間入院し、差額ベッド代や食事代が想定以上にかかりました。
合計18万円の自己負担となり、医療保険未加入を後悔したそうです。
2. 40代・主婦の乳がん治療
長期通院と診断書代、ウィッグ購入費などで年間30万円以上の出費。
保険があれば負担が軽減できたと話しています。
3. 高額な差額ベッド代の請求
混雑で個室利用を余儀なくされ、1泊1万円の出費が続いたケース。
制度外の出費が家計を圧迫したといいます。
4. 先進医療に対応できなかった
がん治療で先進医療を希望したものの、高額な費用により断念。
医療保険の先進医療特約があれば選択肢が広がったと話しています。
5. 長期通院による交通・宿泊費
通院のたびに電車代・ホテル代がかさみ、年間で十数万円の支出。
公的制度では補えない領域に、保険の重要性を感じたそうです。
公的医療制度でどこまでカバーできる?
医療保険が不要とされる背景には、日本の公的医療制度の充実が挙げられます。
代表的な制度の内容を正しく理解することが、保険選びの第一歩です。
| 制度名 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 高額療養費制度 | 医療費の自己負担上限が決まっている | 一時的に全額支払いが必要 |
| 傷病手当金 | 給与の約2/3が最長1年6ヶ月支給 | 自営業・フリーランスは対象外 |
| 出産育児一時金 | 出産費用に対して42万円が支給 | 私的医療保険との併用に注意 |
医療保険が「本当に必要な人」の特徴
公的制度だけでは不安が残る方や、特定の事情を持つ方にとって、民間医療保険は強い味方となります。
以下に該当する方は、加入を前向きに検討しましょう。
1. 貯蓄が少ない
緊急時の出費に耐えられるだけの蓄えがない場合、保険でのカバーが有効です。
医療費が家計に与える影響を抑える手段になります。
2. 自営業・フリーランス
傷病手当金が使えないため、病気やケガで働けない期間の収入補填ができません。
保険加入により、収入減への備えが可能になります。
3. 子どもがいる世帯主
治療や入院による収入減が、生活全体に影響を及ぼします。
家族を守る手段として医療保険を活用する価値があります。
4. 持病があり通院頻度が高い
慢性的な治療費がかかる場合は、保障を受けられるプランを検討しましょう。
医療費負担が長期化するリスクに備える手段として有効です。
5. 先進医療を希望する
がんや難病などで、先進医療を選択する可能性がある方には特約付き保険が適しています。
高額な費用を補償してくれる保険は安心感を与えます。
6. ケガのリスクが高い職業
建設業や運送業など、業務中の負傷リスクが高い職種に該当する場合は備えが必要です。
仕事の性質を加味した保障選びが重要です。
7. 家計に余裕がある
保険料を無理なく支払える方は、「安心を買う」目的での加入が合理的です。
保険を生活コストとして割り切る考えもあります。
医療保険を選ぶ際のポイントと注意点
医療保険を検討する際は、保障内容と家計への影響を総合的に考えることが大切です。
以下の視点を押さえておくと、後悔のない保険選びができます。
1. 必要な保障内容を明確にする
入院、手術、通院、先進医療、三大疾病など、自分のライフスタイルに必要な保障を整理しましょう。
過不足のない保障設計がカギとなります。
2. 掛け捨て型と貯蓄型の違いを理解
掛け捨て型は保険料が安く保障に特化、貯蓄型は将来の返戻金が魅力ですが保険料は高めです。
目的に応じて選択することが重要です。
3. 保障と保険料のバランス
過剰な保障は保険料が高くなりがちです。
必要最小限でコスパよく備えることが、家計の健全性にもつながります。
4. 更新型と終身型のメリット・デメリット
更新型は若いうちは保険料が安いですが、更新ごとに上がる点に注意。
終身型は保険料固定で安定性がある反面、初期負担が大きくなります。
5. 専門家に相談する
保険ショップやFP(ファイナンシャルプランナー)に相談すれば、複数社比較や自分に合った保険選びが可能です。
中立的な視点を持つ専門家の活用がおすすめです。
医療保険に関するよくある質問
Q1. 医療保険は全員に必要ですか?
A. 医療保険は「全員に必須」ではありません。家計や職業、貯蓄状況により必要性は異なります。
自分の状況を客観的に見直すことが大切です。
Q2. 若いうちに入ると本当にお得ですか?
A. 若年期に加入すると、保険料が安く済むメリットがあります。
健康なうちに加入しておくことで、将来のリスクにも備えやすくなります。
Q3. がんや生活習慣病もカバーされますか?
A. 多くの医療保険は三大疾病特約などでがんや生活習慣病に対応しています。
専門保険との組み合わせも検討材料にしましょう。
Q4. 保険料が高くて続けられなさそうです
A. 保険料が家計に負担となる場合は、必要な保障だけに絞ることでコストを抑えられます。
保障内容と保険料の見直しが必要です。
Q5. 医療保険に入っても公的制度は使えますか?
A. はい、民間医療保険と公的制度は併用可能です。
制度の内容と保険の使い分けが重要です。
まとめ|医療保険は「必要かどうか」ではなく「自分に必要かどうか」で判断
医療保険は、すべての人に必ず必要なものではありません。
ですが、自営業や子育て中の方など、リスクが高い方には心強い備えとなります。
公的制度や家計状況を踏まえたうえで、自分に本当に必要な保障を選ぶことが大切です。
監修者からひとこと




スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
医療保険を検討する際、最も重要なのは「自分のライフスタイルや家計と照らし合わせて判断すること」です。
不安だからとりあえず加入するのではなく、公的制度の理解・将来設計・生活リスクの3点から冷静に考えることが大切です。
保険はあくまでリスクに備える手段であり、無理に加入するものではありません。
ぜひ、ご自身にとって本当に必要な保障かどうかを見極めて、納得のいく選択をしてください。