

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
保有資格
AFP・2級FP技能士
専門分野・得意分野
生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。
個人事業主が家族を扶養に入れる場合、税制と社会保険で基準が異なります。制度を正しく理解しないと、控除や保険料で損をする可能性があります。
この記事では、税制上・社会保険上の扶養基準の違い、手続きの流れ、年収変動時の注意点、そして家計を守る医療保険の活用法まで、実務に役立つ情報をわかりやすく解説します。
個人事業主の扶養制度の基礎
個人事業主は会社員とは異なり、加入している社会保険制度や税控除の使い方が変わります。扶養の基準もその影響を受けます。
特に国民健康保険や国民年金加入者の場合、会社員のような「社会保険の扶養」という概念がありません。
1. 税制上の扶養控除
個人事業主の場合も、税制上の扶養控除は利用できます。扶養親族の年間所得が48万円以下(給与収入のみなら103万円以下)であれば適用されます。
確定申告で適用するため、扶養親族の所得を年間で確認することが重要です。
2. 配偶者控除・特別控除
配偶者控除は年収103万円以下、配偶者特別控除は150万円程度まで段階的に適用されます。
青色申告専従者給与を支給している場合は、控除適用が制限される点に注意しましょう。
3. 国民健康保険の家族加入
国民健康保険には「扶養」という概念がなく、家族それぞれに保険料がかかります。
ただし、自治体によっては世帯割の軽減措置があるため、加入先で確認が必要です。
4. 国民年金の第3号被保険者制度
第3号被保険者は厚生年金加入者の扶養配偶者が対象です。個人事業主はこの制度を利用できません。
扶養配偶者も国民年金第1号被保険者として保険料を納める必要があります。
5. 扶養手続きの必要書類
税制上の扶養は確定申告書に記載します。マイナンバーや所得証明など、必要書類は事前に準備しましょう。
国民健康保険・国民年金の手続きは自治体窓口で行います。
年収変動時の家計防衛策
個人事業主は収入が変動しやすく、扶養基準や保険料負担にも影響します。
年収が増えた場合は税負担や社会保険料が上がるため、固定費の見直しが重要です。
家計防衛のための見直し手順
1. 医療保険の保障額調整
高額療養費制度を踏まえ、自己負担分と生活費不足分を補える額に設定します。
女性特有疾病への備えを加えると、長期入院時のリスクに強くなります。
2. 就業不能保険の活用
病気やケガで働けなくなったときの収入減に備えます。特に個人事業主は傷病手当金がないため重要です。
保障期間と給付開始までの日数を確認して選びましょう。
家計防衛のヒント
保険は「生活費の谷間」を埋める額だけ確保し、過剰契約を避けましょう。
3. 事業経費と家計費の分離
事業用口座と家計用口座を分けることで、収支管理が明確になります。
扶養基準の判定や確定申告の精度も上がります。
4. 予備資金の確保
売上減少や病気時に備え、生活費3〜6か月分を現金で用意します。
事業用と家計用の両方で準備すると安心です。
5. 節税と保障のバランス
生命保険料控除や小規模企業共済など、節税しながら保障を確保できる制度を活用します。
長期的な事業計画と家計の安定を両立しましょう。
注意ポイント
節税目的だけで保険加入すると、必要な時に役立たない保障になることがあります。
FPに聞く!個人事業主の扶養と家計のリアルQ&A

個人事業主が家族を扶養に入れるときの疑問をFPが解説します。
34歳・女性
個人事業主でも配偶者控除は使えますか?
スマホdeほけん
はい、使えます。ただし専従者給与を支給している場合は適用できません。
34歳・女性
国保に扶養制度はありますか?
スマホdeほけん
ありません。家族それぞれに保険料がかかります。
34歳・女性
年収が変動した場合の注意点は?
スマホdeほけん
税負担や保険料が変わるので、予備資金と固定費見直しが必要です。
34歳・女性
医療保険は必要ですか?
スマホdeほけん
はい。個人事業主は傷病手当金がないため、入院や手術で収入が途絶えた場合の備えになります。
34歳・女性
扶養と保険の見直しは同時にすべきですか?
スマホdeほけん
同時に行うと、税・保険料・保障のバランスを一度に整えられます。
個人事業主の扶養と家計に関するQ&A

Q1. 個人事業主の扶養控除は会社員と同じですか?
A. 基本的に同じですが、専従者給与を支給している場合は制限があります。
Q2. 国保の保険料軽減はありますか?
A. 所得や世帯構成に応じた軽減制度があります。
Q3. 医療保険は必須ですか?
A. 必須ではありませんが、リスクに備える意味で有効です。
Q4. 配偶者特別控除は使えますか?
A. 条件を満たせば使えます。
Q5. 年収判定はいつ行うべきですか?
A. 確定申告前に行うと、控除漏れを防げます。
まとめ
個人事業主が家族を扶養に入れる際は、税制と社会保険の違いを理解し、基準や手続きを正確に押さえることが重要です。収入変動に備え、医療保険や予備資金を活用しながら家計の安定を図りましょう。
制度理解+家計防衛で、長期的に安定した経営と生活を両立できます。
公的・公式リンク集
扶養や保険の基準は制度改正で変わる可能性があります。必ず公式情報で確認しましょう。
自治体や加入先の健康保険組合の情報も定期的に確認してください。
監修者からひとこと




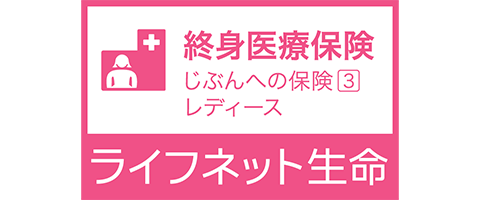
スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
個人事業主は収入の変動が大きく、扶養の基準や保険料負担も変わりやすい立場です。制度の違いを理解し、収入が増えた場合の税負担や社会保険料のシミュレーションを行うことが大切です。
また、医療保険や就業不能保険の活用は、突発的なリスクから家計を守るために有効です。毎年の確定申告前に扶養と保障を同時に見直す習慣を持ちましょう。