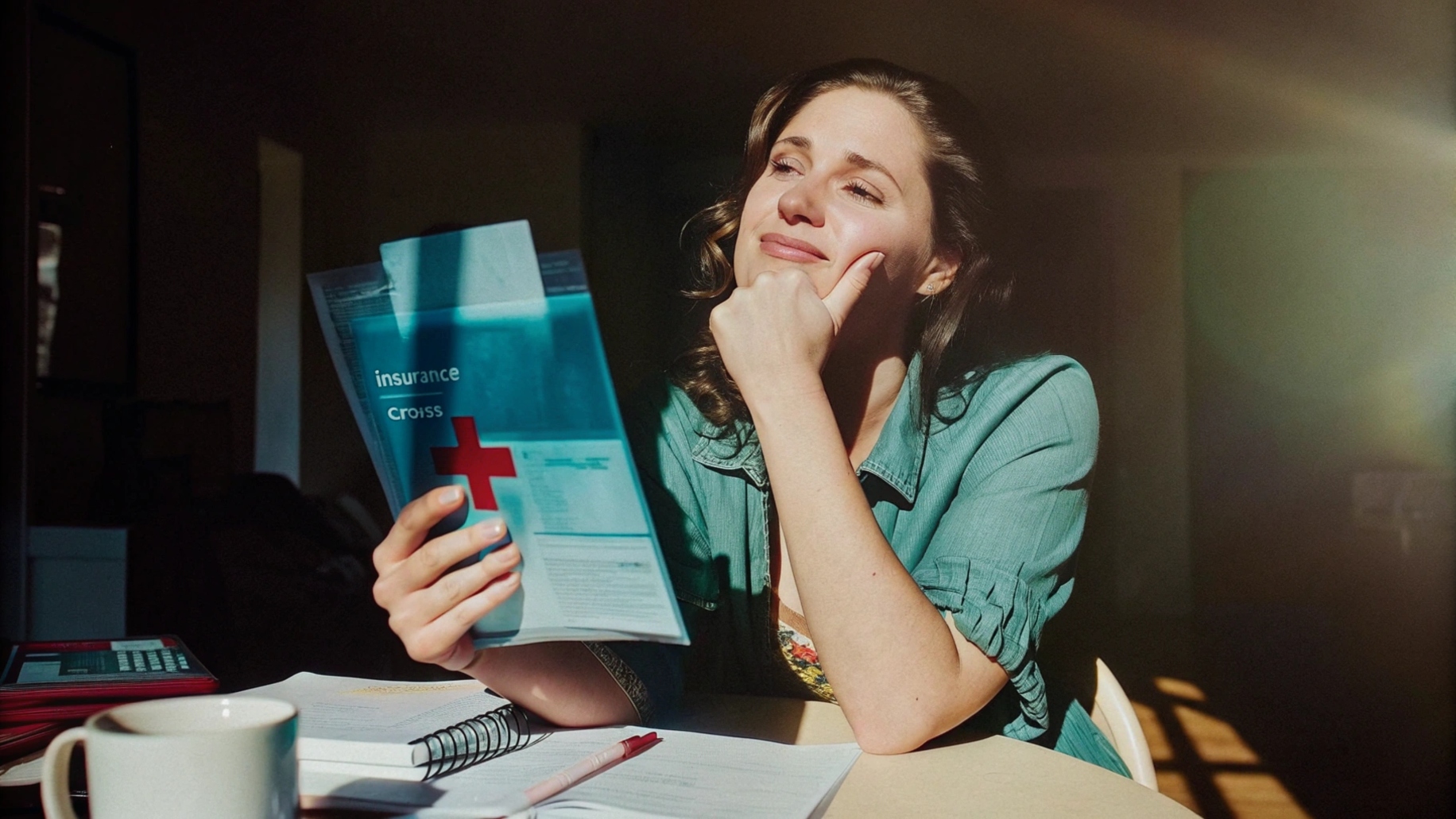

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
保有資格
AFP・2級FP技能士
専門分野・得意分野
生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。
「高額療養費制度があるから医療保険はいらないのでは?」
「病気になっても貯蓄でカバーできるから必要ないかも…」
日本の医療制度は充実しており、公的医療保険によって多くの医療費がカバーされます。そのため、「医療保険は不要」と考える人も少なくありません。しかし実際には、治療費以外の出費や就業不能による収入減など、公的保障だけでは補いきれないリスクが存在します。
この記事では、医療保険はいらないのかと考える方に向けて、本当に不要かどうかを判断するための視点と、備えが必要となるケースについて解説します。
医療保険が「いらない」と考えられるケース
医療保険が不要と考えられる4つのパターン
1.高額療養費制度を正しく理解している
日本には高額療養費制度があり、医療費の自己負担額には月ごとに上限が設けられています。この仕組みを理解していれば、保険で過剰に備える必要はありません。ただし、差額ベッド代や先進医療費は対象外です。
2.貯蓄で医療費が十分にまかなえる
治療費や療養中の生活費を貯蓄でカバーできる場合、医療保険は必ずしも必要ありません。病気やケガによる収入減も考慮し、生活資金3~6か月分以上の備えがあるかが判断の目安です。
3.勤務先に医療費補助や共済がある
企業によっては、医療費補助や共済制度が整っている場合があります。これらの保障内容を確認することで、医療保険の必要性が変わってきます。
4.健康状態が良好でリスクが低いと判断できる
年齢が若く、健康診断でも特に問題がない場合は、すぐに医療保険が必要とは限りません。ただし、将来のライフステージ変化(結婚・出産・加齢)を見据えた上での判断が必要です。
医療保険が必要かどうかを見極めるポイント
医療保険が必要か判断する3つの視点
1.公的保障と自己資金のバランスを把握する
高額療養費制度や傷病手当金などの公的保障でどこまでカバーできるかを理解し、不足部分を貯蓄で補えるかをチェックします。足りない部分がある場合は医療保険で補うのが合理的です。
2.収入減リスクも含めて考える
治療期間中に仕事を休む場合、特に自営業やフリーランスは収入減の影響が大きくなります。生活費の補填まで考えるなら、医療保険や就業不能保険の活用も選択肢となります。
3.治療費以外の支出を想定する
交通費や差額ベッド代、付き添い家族の宿泊費など、医療費以外にも負担がかかるケースがあります。これらも含めて備える必要があるかを検討しましょう。
医療保険は「公的保障と貯蓄で補えない部分」をカバーする備え
医療保険は、公的医療保険や自己資金(貯蓄)ではまかなえない医療費を補うための手段です。
必要性をしっかり見極め、過不足のない保障設計を心がけましょう。
よくある質問 Q&A
Q1. 若いうちは医療保険は必要ありませんか?
A 若いうちは健康リスクが低いため、必ずしも医療保険が必要とは限りません。ただし、治療費以外の出費や収入減をどう補うかを考慮することが大切です。
Q2. 高額療養費制度があれば医療保険はいらないのでは?
A 高額療養費制度で医療費の上限はありますが、差額ベッド代や先進医療費、通院交通費は対象外です。これらをどう備えるかが判断ポイントです。
Q3. 自営業でも医療保険は不要ですか?
A 自営業者は傷病手当金がないため、就業不能時の収入減リスクが高くなります。必要性は会社員より高いケースが多いので慎重に検討しましょう。
Q4. 通院保障は必要ですか?
A 現在の医療事情では通院治療が増えています。入院保障だけでは不足するケースが多いため、通院保障付き設計が効果的です。
Q5. 医療保険は途中で見直すべきですか?
A はい、家族構成や収入状況が変わった場合や医療技術の進歩によって必要な保障内容は変わります。5年ごとの見直しがおすすめです。
まとめ
医療保険は、「必要な人に必要な分だけ」を備えることが基本です。高額療養費制度や傷病手当金といった公的保障を正しく理解し、貯蓄や勤務先の制度で補える部分がどこまでなのかを冷静に把握することが大切です。
治療費以外の出費や収入減の影響まで考慮し、「何となく不安だから」ではなく、具体的なリスクをもとに加入の判断をすることが家計にとって合理的な選択につながります。
ライフステージの変化に応じた定期的な見直しも意識しながら、無駄のない保障設計を行いましょう。
監修者からひとこと




スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
医療保険は「安心のため」だけで加入するものではありません。公的保障の仕組みと自己負担の範囲を理解したうえで、不足するリスクを合理的に補う設計が大切です。
特に高額療養費制度の存在は大きいものの、差額ベッド代や先進医療費、長期通院による交通費など、対象外の費用が意外と多く存在します。これらをどう備えるかがポイントです。
また、収入減リスクについても見逃せません。特に自営業やフリーランスの方は傷病手当金がないため、医療費と生活費の両面から設計を考える必要があります。
「何となく不安」ではなく、数字と制度を正しく理解し、必要な保障を必要な分だけ持つ。この視点を持つことで、安心と家計の健全性を両立する医療保険選びができるでしょう。