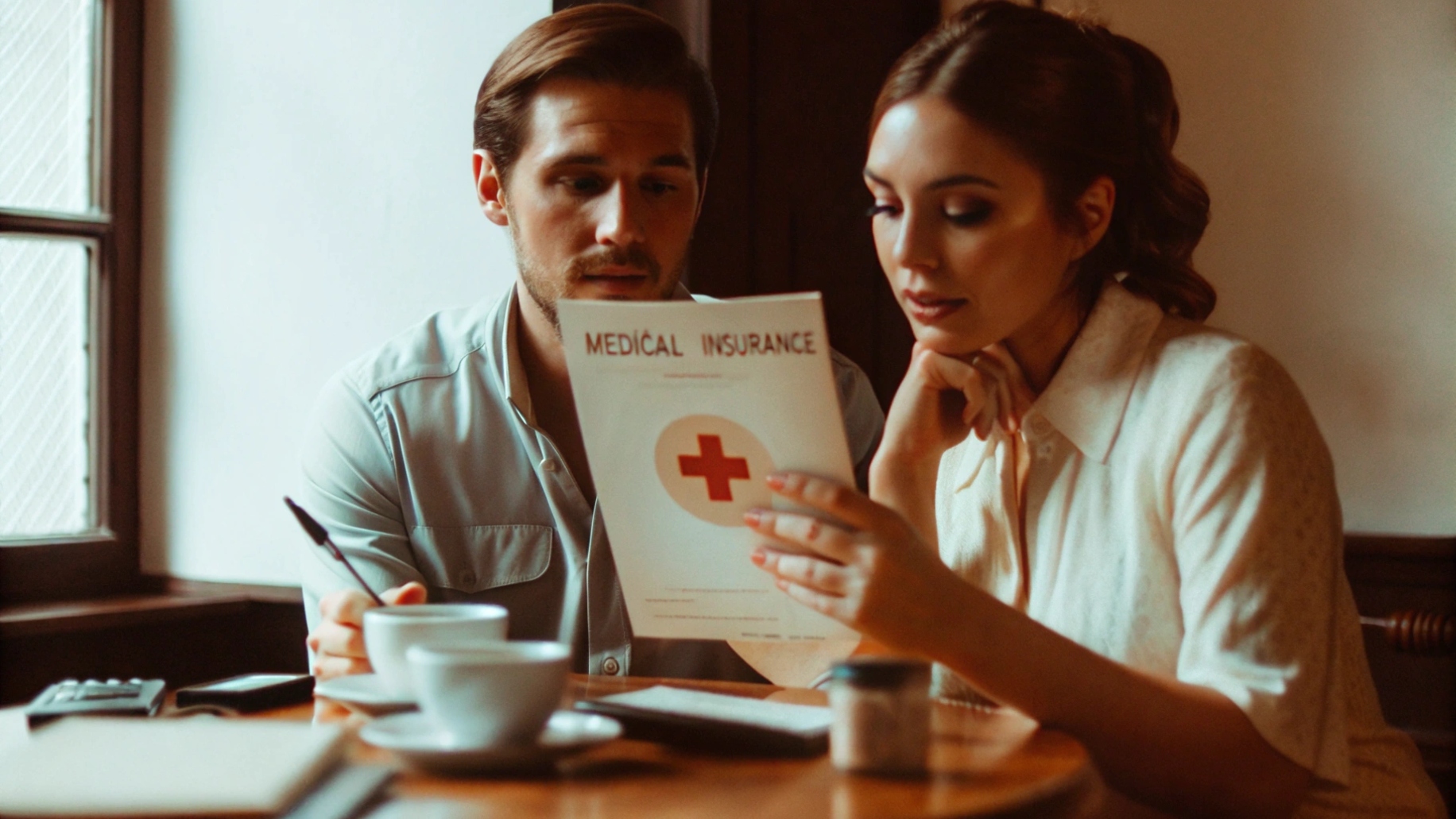

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
保有資格
AFP・2級FP技能士
専門分野・得意分野
生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。
「医療保険って入るべきなの?」
「高額療養費制度があるから、いらないのでは?」
医療保険は、病気やケガによる医療費負担を軽減するための備えとして広く利用されています。しかし、日本には健康保険や高額療養費制度といった公的保障があるため、「医療保険は不要」という意見もあります。
この記事では、医療保険は必要かについて、公的保障と自己負担のバランスをふまえ、加入の必要性を冷静に判断するための考え方と、選び方のポイントを解説します。
医療保険が「必要」と考えられる理由
1.高額療養費制度ではカバーできない費用がある
日本の公的医療保険には自己負担限度額を設ける高額療養費制度がありますが、差額ベッド代、先進医療費、自由診療、通院交通費、家族の付き添い宿泊費などは対象外です。これらの自己負担分をどうカバーするかが医療保険の役割です。
2.医療技術の進歩で通院治療が中心になっている
医療技術が進化し、入院期間は短縮されています。その一方で、退院後の通院治療が長引くケースが増えており、通院保障のある医療保険が必要とされる背景です。
3.治療に伴う生活費や付随費用の負担がある
治療に直接かかる医療費以外にも、交通費や食事代、家族の付き添い費用、仕事を休むことで生じる収入減など、多くの費用が発生します。こうした費用を準備する手段のひとつが医療保険です。
4.長期療養による収入減リスクがある
長期間仕事を休む場合、会社員なら傷病手当金で一部補填されますが、満額ではありません。自営業・フリーランスはさらに保障が薄いため、医療保険や就業不能保険でカバーする必要があります。
医療保険選びで押さえたいポイント
1.公的保障との役割分担を理解する
高額療養費制度や傷病手当金など、公的制度でカバーできる範囲とカバーできない範囲を整理することが大切です。公的保障では足りない部分を補うのが民間保険の基本的な考え方です。
2.通院・入院・手術の保障バランスを考える
入院日額型だけでは対応しきれないケースが増えています。手術給付金、通院保障、一時金タイプなどを組み合わせ、現在の医療事情に合った設計を意識しましょう。
3.保険料と保障内容のバランスを見直す
保障が厚すぎると保険料が高くなり、家計を圧迫します。必要な保障額を適切に設定し、ライフステージごとに見直すことが、無理なく安心できる保険設計につながります。
医療保険は「公的保障で不足する部分を補う備え」
医療保険は、公的医療保険ではカバーしきれない自己負担分を補う役割を持ちます。
必要性をしっかり見極め、無理のない保障設計で安心できる備えを整えましょう。
よくある質問 Q&A
Q1. 医療保険は若いうちから必要ですか?
A 若いうちは医療リスクが低いものの、突発的なケガや病気、長期通院が必要になる可能性はゼロではありません。必要保障額と保険料のバランスを考えましょう。
Q2. 高額療養費制度があれば医療保険は不要ですか?
A 高額療養費制度で医療費負担は軽減できますが、差額ベッド代や先進医療費、通院交通費は対象外です。これらをどう備えるかが医療保険のポイントです。
Q3. 会社員でも医療保険は必要でしょうか?
A 会社員は傷病手当金がありますが、満額ではありません。入院が長期化したり、通院治療が続く場合には医療保険が役立つケースがあります。
Q4. 自営業・フリーランスは医療保険に入るべきですか?
A はい。自営業・フリーランスには傷病手当金がないため、入院・通院に伴う収入減リスクへの備えとして医療保険の必要性が高いです。
Q5. 医療保険は途中で見直すべきですか?
A はい。医療事情や家族構成の変化によって必要な保障は変わります。5年ごとの見直しが安心です。
まとめ
医療保険は、「公的保障の限界と自己負担のバランスを見極めたうえで、必要な分だけ備える」ことが大切です。高額療養費制度や傷病手当金といった仕組みが整っているものの、差額ベッド代や先進医療費、通院時の交通費、長期療養による収入減などは公的保障だけでは対応できません。
過剰な保険加入は保険料のムダにつながりますが、必要な保障を持たないことは将来の不安要因になります。冷静にリスクを見極め、自分に合った適切な保障設計を行うことが、無理なく安心できる医療保険選びにつながります。
ライフステージや健康状態に応じて定期的に見直すことで、過不足のない備えが実現できます。
監修者からひとこと




スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
医療保険に加入するかどうかを考える際、まず大切なのは、公的医療保険と高額療養費制度の仕組みを正しく理解することです。これらを前提に、不足する部分をどう補うかを冷静に判断する必要があります。
特に差額ベッド代や先進医療、通院にかかる費用は、公的保障の対象外となることが多く、自己負担が想定以上に大きくなるケースがあります。さらに、長期間働けない場合の収入減への備えも重要です。会社員と自営業・フリーランスでは状況が異なるため、自身の働き方に合わせた設計が求められます。
「安心だから加入する」のではなく、数字と制度に基づいた合理的な判断で設計を行うことが賢明です。必要な保障を、必要な分だけ準備する。この視点を持つことで、家計の健全性と安心感を両立できるでしょう。