

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
保有資格
AFP・2級FP技能士
専門分野・得意分野
生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。
「生命保険を解約したら返戻金に税金はかかるの?」
「どのタイミングで、どんな税金が発生するの?」
生命保険や学資保険を解約したときに受け取る解約返戻金。このお金に対して税金がかかる場合があることをご存じでしょうか?
実は、保険の種類や契約形態、払込保険料の総額によって、課税される税金の種類が変わります。何も知らずに受け取ると「想定外の税負担」に戸惑うことも。
この記事では、保険 解約 返戻 金 税金について、課税対象になる条件や計算方法、注意点をわかりやすく解説します。
保険解約返戻金に税金がかかる理由と必要性
利益(払戻差益)が生じる場合は課税対象になる
解約返戻金が、それまで支払った保険料の総額を上回る場合、その差額部分が「利益(払戻差益)」とみなされ、税金がかかります。
契約者と被保険者・受取人の関係で課税区分が変わる
契約者・被保険者・受取人が同一人物かどうかで、所得税(または住民税)、相続税、贈与税のどれが適用されるかが変わります。契約形態の確認が必要です。
一時所得として課税されることが多い
多くの場合、解約返戻金は「一時所得」に分類され、特別控除(最大50万円)と課税計算が行われます。正しい計算方法を知っておくことが大切です。
相続税や贈与税がかかるケースもある
契約者・被保険者・受取人が異なる場合には、相続税または贈与税の対象になることがあります。課税区分の違いを理解しておく必要があります。
解約返戻金を受け取るときの選び方・注意ポイント
解約返戻金の税金対策で押さえたい3つのポイント
契約形態(契約者・被保険者・受取人)を必ず確認する
税金の種類が変わるため、誰が契約者で誰が受取人かを必ず確認しましょう。同一人物の場合は所得税、それ以外は相続税や贈与税となるケースがあります。
解約返戻金の利益(差益)を把握する
解約返戻金と払込保険料の合計額との差額が課税対象となります。税金がかかる金額はこの「利益部分」だけです。
一時所得の特別控除を活用する
一時所得には年間50万円の特別控除があります。ほかの一時所得と合算して計算されるため、複数の解約や満期金受け取りがある場合は合計額に注意しましょう。
保険の解約返戻金は「課税対象になる場合がある」。
契約形態と利益額をしっかり確認し、賢く受け取りましょう。
よくある質問 Q&A
Q1. 解約返戻金を受け取ったら必ず税金がかかりますか?
A いいえ。解約返戻金が払込保険料の総額を超えた場合、その差額(利益)が課税対象です。元本割れしている場合は税金はかかりません。
Q2. 解約返戻金が一時所得になるのはどんな場合ですか?
A 契約者・被保険者・受取人が同一人物で、解約返戻金を受け取った場合は一時所得となります。特別控除50万円を適用できます。
Q3. 贈与税や相続税がかかるケースはどんなときですか?
A 契約者と受取人が異なる場合、贈与税や相続税が適用されます。契約形態によって税金の種類が異なるため、確認が必要です。
Q4. 一時所得はどのように計算しますか?
A (解約返戻金 − 払込保険料総額 − 特別控除50万円)×1/2が課税対象の金額です。確定申告が必要になる場合もあります。
Q5. 解約返戻金を複数の保険で受け取った場合はどうなりますか?
A 一時所得はすべて合算して計算されます。複数の解約返戻金がある場合は合計額で判断し、50万円の特別控除を適用します。
まとめ
生命保険や学資保険を解約して受け取る返戻金は、契約形態と利益(差益)の有無によって税金がかかる場合があります。すべての返戻金に税金がかかるわけではありませんが、課税対象になるケースを理解しておくことが大切です。
特に、契約者・被保険者・受取人の関係性によって、所得税・相続税・贈与税といった異なる税区分が適用されます。この仕組みを知らずに受け取ってしまうと、思わぬ税負担が発生することもあります。
解約を検討するときは、受け取り時の税金も含めてシミュレーションし、無理のないタイミングと適切な金額で受け取ることが安心につながります。事前に税金の仕組みを理解して、後悔のない解約判断を行いましょう。
監修者からひとこと


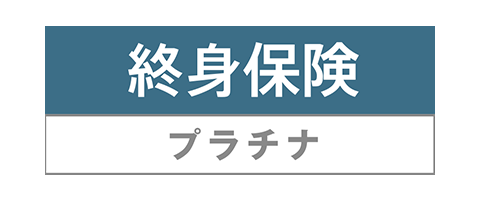
スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
解約返戻金に対する課税は、契約者・被保険者・受取人の組み合わせによって大きく異なります。この税区分を理解していないと、受け取ったときに「予想外の税金がかかる」と驚くケースも少なくありません。
特に、一時所得に該当する場合には「50万円の特別控除」が活用できる反面、複数の返戻金を受け取った場合は合算して計算されるため注意が必要です。確定申告が必要になる場合もあるため、事前に準備しておくことが大切です。
保険の解約は単に「お金が戻る」というだけではなく、税金・将来設計・保障のバランスを考えたうえで判断することが重要です。納得できる解約をするためには、税制の仕組みもふまえた総合的な視点を持つことをおすすめします。