

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
保有資格
AFP・2級FP技能士
専門分野・得意分野
生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。
「持病があるけど、どの保険を選べばいいのかわからない」
「引受基準緩和型の保険選びで失敗したくない」
このような悩みを持つ方は少なくありません。持病があると保険選びの選択肢は限られますが、現在では多様な商品が登場しており、自分に合ったものを選ぶことが可能です。
この記事では、引受基準緩和型保険を選ぶ際のポイントと、後悔しないためのチェック項目についてわかりやすく解説します。
引受基準緩和型保険を選ぶべき理由とおすすめの特徴
おすすめされる引受基準緩和型保険の4つの特徴
1. 告知が簡単で加入しやすい
一般的な医療保険に比べ、告知項目が限定されており、慢性疾患や既往症があっても比較的スムーズに加入できます。
2. 必要な保障に絞ったシンプル設計
過剰な保障を付けず、必要最低限の医療費リスクに絞ったシンプルな設計の保険が主流です。無駄なコストを抑えられます。
3. 保険料の負担を抑えられる
無選択型保険に比べて保険料が割安に設定されている商品も多く、家計への負担を抑えつつ万一に備えることができます。
4. 契約後の保障内容が手厚いタイプがある
一部の商品では、契約から一定期間経過後に通常の医療保険並みの保障が受けられるタイプもあり、長期保障を重視する方に適しています。
引受基準緩和型保険選びで後悔しないためのチェックポイント
選び方で押さえたい3つの視点
1. 免責期間と待機期間を必ず確認する
加入直後は一定期間、保障対象外となる場合があるため、免責期間(例:90日間)や待機条件を必ず確認しましょう。
2. 保険料と保障内容のバランスを取る
保険料が安くても保障が不足していては意味がありません。必要な保障を確保しつつ、無理なく続けられるプランを選びましょう。
3. 付帯サービスやサポート体制も比較する
契約者向けの健康相談サービスや医療サポートが充実しているかどうかも、保険選びの重要な比較ポイントとなります。
引受基準緩和型保険は「持病と向き合いながら未来を守るための選択」
加入ハードルが下がったとはいえ、免責期間や保障範囲の制限をきちんと理解することが必要です。
保障が手厚いタイプや、付帯サポートが充実している商品を選ぶことで、万一のときも安心感が得られます。
自分のライフプランに合わせた無理のない設計と、将来的な見直し余地も意識しながら慎重に選択しましょう。
よくある質問 Q&A
Q1. 引受基準緩和型保険は本当に誰でも加入できますか?
A すべての方が無条件で加入できるわけではありません。重度の持病や入院中の場合など、引受不可となるケースもあります。
Q2. 加入後すぐに給付金は受け取れますか?
A 多くの商品で90日程度の免責期間が設けられています。期間中に発症・入院した場合、給付金対象外となることがあるため注意が必要です。
Q3. 引受基準緩和型保険と無選択型保険の違いは何ですか?
A 引受基準緩和型は簡単な告知が必要ですが、無選択型は告知なしで加入できます。ただし無選択型のほうが保険料は割高になります。
Q4. 健康状態が改善した場合、通常型保険に切り替えられますか?
A 保険会社によっては切り替えを認めているところもありますが、原則は新たに通常型に再加入する形になります。
Q5. 特約は付けたほうがよいでしょうか?
A がん保障や女性疾病保障など、ライフステージに応じた特約は有効です。ただし、保険料負担とのバランスを考慮しましょう。
まとめ
引受基準緩和型保険は、持病があっても備えを諦めずに済む大切な選択肢です。
加入しやすさだけでなく、保障内容や保険料負担のバランス、そして免責期間や付帯サービスまで、総合的に比較することが重要です。
将来を見据えたうえで、無理のないプランを選び、定期的な見直しも視野に入れていきましょう。
監修者からひとこと



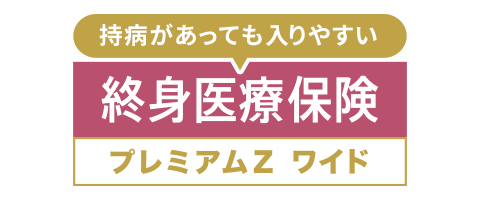

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
引受基準緩和型保険は、これまで保険加入が難しかった方々にも、安心を提供できる素晴らしい選択肢です。医療技術の進歩とともに、保険商品の柔軟性も高まっており、より多くの人にとって現実的な備えが可能になりました。
しかし、加入しやすい反面、保障範囲や免責期間といった「見えにくいリスク」にも目を向けることが大切です。目先の安心だけでなく、長期的な視点でライフプランに沿った保険選びを意識しましょう。
人生のリスクに備えるために、保険は非常に重要なツールです。正しい知識を持ち、自分自身で最適な選択をする力を養うことが、将来の安心につながります。