

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
保有資格
AFP・2級FP技能士
専門分野・得意分野
生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。
糖尿病予備群や軽度の糖尿病と診断されている方にとって、HbA1c(グリコヘモグロビン)値は重要な健康指標です。
しかし、一般の医療保険ではHbA1c値の高さを理由に加入を断られるケースも少なくありません。そんな中で注目されているのが「引受基準緩和型医療保険」です。本記事では、HbA1c値に不安がある方でも医療保険に加入するための方法やポイントを解説します。
引受基準緩和型医療保険とは?
過去の通院歴や検査数値に不安があっても、告知項目が限定的であるため加入しやすい医療保険です。
通常3つ程度の簡易な質問に答えるだけで申込可能で、HbA1cがやや高めの方でも対象となるケースが多く見られます。
HbA1c値と医療保険審査の関係
HbA1cは過去1〜2か月の平均血糖値を示す指標で、6.5%以上は糖尿病と診断されます。
保険会社によっては、6.0〜6.4%程度でも加入を断ることがあり、数値による線引きが審査において重要視されます。
注意ポイント
直近のHbA1c値が7.0%を超えていると、緩和型保険でも加入できないケースがあるため、最新の検査結果を把握しておきましょう。
こんな方におすすめ
HbA1cの数値に不安がある方でも、以下に当てはまる場合は引受基準緩和型医療保険を検討すべきです。
1. 検診で6.0%〜6.9%の数値が出た
この範囲のHbA1cは境界型とされ、将来的に糖尿病へ移行するリスクがあります。
今のうちに備えることで、治療費負担を軽減できます。
2. 食事療法のみで経過観察中
薬を使用していない場合、緩和型医療保険に加入できる可能性が高いです。
診断書や治療計画書の提出が求められる場合もあります。
3. 以前の保険に加入を断られた
過去の審査落ちがあっても、緩和型で再チャレンジできるチャンスがあります。
数値が安定していれば、加入の可能性は十分にあります。
4. 糖尿病家系で将来が不安
家族に糖尿病患者が多い場合、予防的な観点から保障を用意するのが賢明です。
保障範囲を限定した低価格プランも選択肢に含めましょう。
5. 万一の入院費を備えておきたい
糖尿病の合併症による入院・通院が将来発生する可能性もあります。
早めの加入で、そのリスクを軽減できます。
HbA1cと医療保険に関するよくある質問

Q1. HbA1cが7.0%を超えている場合でも加入できますか?
A. 多くの緩和型医療保険では、7.0%を超えると加入が難しくなります。
ただし、基準は保険会社によって異なるため、最新の条件を確認しましょう。
Q2. 薬を服用していても加入できますか?
A. 一部の緩和型医療保険では、投薬中でも加入可能です。
ただし、インスリン治療や合併症がある場合は対象外となるケースがあります。
Q3. 加入時に提出が必要な書類は?
A. 多くの場合、告知書のみで申込可能です。
ただし、状況によっては診断書や検査結果の提出を求められることもあります。
Q4. 通院していても保険に入れますか?
A. 食事療法や軽度の経過観察のみなら、加入できる可能性が高いです。
治療内容と直近の数値によって判断されます。
Q5. 保険料は通常の医療保険と比べて高いですか?
A. はい、緩和型はリスクが高いため、一般的に保険料は割高です。
そのため、必要な保障だけを選んでコストを抑える工夫が重要です。
まとめ
HbA1cの数値が高めでも、引受基準緩和型医療保険であれば加入の道が開けます。
検査数値の安定性・治療歴の有無・通院状況を正確に把握し、複数社の商品を比較検討することで、より良い保険選びが実現できます。
監修者からひとこと



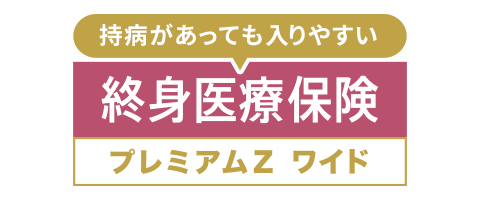

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
HbA1c値は生活習慣病の予兆として非常に重要な指標であり、将来的な医療リスクを早期に捉える材料になります。
そのため、数値に不安を感じた段階で医療保険を検討するのは極めて有効です。緩和型医療保険は、こうした方のための受け皿として機能しますが、保障の範囲や給付条件をよく理解することが大切です。