

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
保有資格
AFP・2級FP技能士
専門分野・得意分野
生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。
胃腸炎は一過性のものから慢性化するものまで多岐にわたりますが、繰り返し症状が出る方にとっては、将来的な医療費負担が不安材料のひとつとなります。
特に持病として慢性的な胃腸炎を抱えている場合、通常の医療保険への加入は困難になることが多く、加入を諦める方も少なくありません。しかし、引受基準緩和型医療保険であれば、過去の治療歴があっても加入可能な場合があり、必要な備えを得ることができます。本記事では、胃腸炎の持病や既往歴がある方向けに、引受基準緩和型医療保険の基本や、選ぶ際に注意したいポイントを詳しく解説します。
引受基準緩和型医療保険とは?
通常の医療保険に比べて、健康状態に関する告知項目が少なく、持病や既往症がある方でも加入しやすいのが特徴です。
「直近○年以内に入院・手術歴がないか」など限定的な告知内容で審査が行われるため、胃腸炎で過去に入院歴があっても対象になるケースが多くあります。
加入時に確認したいポイント
引受基準緩和型医療保険に加入する際は、保障内容や支払い条件を細かく確認する必要があります。
特に胃腸に関する保障範囲や免責期間、特定部位不担保の有無などをチェックし、将来の支払い対象外とならないように注意しましょう。
注意ポイント
持病の内容によっては「胃・腸」に関する給付対象が限定される場合があります。
どんな人に向いている?
以下に該当する方には、引受基準緩和型医療保険の加入を検討する価値があります。
1. 慢性胃腸炎で通院中
定期的に内科で通院している方でも、一定の条件を満たせば加入できる保険があります。
現在の通院頻度や症状の安定性が審査のポイントとなります。
2. 過去に胃潰瘍・十二指腸潰瘍の治療歴あり
過去に治療歴がある方も、完治後一定期間経過していれば加入できるケースがあります。
加入前に、診療記録や治癒証明の提出を求められることもあるため、準備しておくと安心です。
3. 一般の医療保険で審査に落ちた経験がある
健康告知のハードルが高い一般の医療保険で審査に通らなかった方には、緩和型が有力な選択肢です。
現在の体調をもとに審査されるため、直近の医療履歴を整理してから申し込みましょう。
4. 再発リスクが高いと指摘された
医師から再発リスクがあると伝えられている場合、万が一に備える保障は必要不可欠です。
保険会社によっては、リスクに配慮した保障設計が可能な商品もあります。
5. 保障内容を限定してでも備えたい
すべての病気に対応できなくても、最低限の入院給付金だけでも確保したいというニーズにも対応しています。
保険料を抑えながら必要な保障が得られるため、コスト重視の方にも適しています。
よくある質問(Q&A)

Q1. 胃腸炎の既往歴があると通常の医療保険に入れませんか?
A. はい、通常の医療保険では告知項目が厳しいため、胃腸炎の入院や通院歴があると加入が難しい場合があります。
その場合は、引受基準緩和型医療保険が有力な選択肢になります。
Q2. 緩和型医療保険は保険料が高いのですか?
A. 一般の医療保険よりやや高めに設定されています。
ただし、加入しやすさと保障確保のバランスを考えると、持病がある方には価値があります。
Q3. 胃腸炎に関する保障は制限されますか?
A. 場合によっては、加入後一定期間は免責(給付対象外)となることがあります。
免責期間や特定部位不担保の有無を契約前に必ず確認してください。
Q4. 今も胃腸炎で通院中ですが加入できますか?
A. 通院中でも加入できるケースはありますが、症状の安定性や通院頻度が審査のポイントになります。
まずは保険会社に告知して相談することをおすすめします。
Q5. 胃腸炎以外の病気も保障されますか?
A. はい、多くの緩和型医療保険では胃腸炎以外の病気やケガも対象です。
ただし、商品によって保障範囲や条件が異なるため、複数社の比較が重要です。
まとめ
胃腸炎を持病として抱えている方でも、引受基準緩和型医療保険であれば医療保障を受けられる可能性があります。
重要なのは、自分の病歴に合った保険商品を見極めることと、保険料と保障内容のバランスを考えた上で、慎重に選択することです。また、いくつかの保険会社を比較することで、自分にとって最適なプランに出会える可能性が高まります。
監修者からひとこと



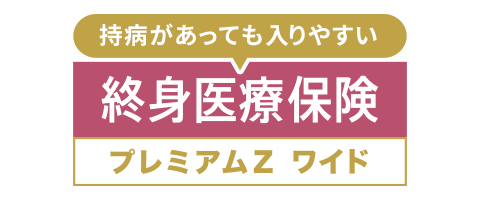

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
胃腸炎は一見軽症に思われがちですが、再発性や慢性化によって通院や検査の頻度が高くなることもあり、医療費の負担が無視できません。
そういった背景から、持病がある方でも加入しやすい引受基準緩和型医療保険は有効な選択肢となります。ただし、緩和型保険は一般の医療保険と比較して制限や保険料の高さがあるため、保険選びは専門家と相談しながら慎重に進めることが望ましいでしょう。告知内容の把握と保障内容の比較が、将来の医療費リスクに備える鍵となります。