

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
保有資格
AFP・2級FP技能士
専門分野・得意分野
生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。
「収入は変わらないのに貯金が増えない…」と感じたら、最優先は固定費の見直しです。毎月の支出を恒常的に下げることが、最小労力で最大効果を生むからです。
本記事では、通信・保険・サブスク・住居などの削減手順を整理し、浮いたお金を老後資金や資産形成へ回す実践策をプロが解説します。今日から着手できるチェックリスト付きです。
固定費見直しの基本|効果が大きい順に着手しよう
固定費は一度見直すと効果が毎月続きます。まずは金額インパクトが大きい項目から進めましょう。
削減額×継続月数が家計インパクトです。見直し優先度の判断軸を先に決めると途中で迷いません。
まず削減すべき固定費の優先順位|すぐ効く5分野
実行ハードルが低く、削減幅が大きい分野から攻めます。手続きはスマホと明細さえあれば完了します。
以下の順に着手すれば、無理なく合計1〜3万円の削減も現実的です。
1. 通信費:大手→格安SIM
現在の利用量に合うプランへ乗り換えると、月額が数千円下がることがあります。
家族割よりも個別最適が有利なケースが多いので、データ量と通話習慣を見直しましょう。
2. 光熱費:電力・ガスの切替
使用量と世帯人数に合う料金メニューへ変更すると、年間で数千円〜数万円の差が生まれます。
季節変動を考慮し、セット割やポイント還元を含めて実質コストで比較します。
3. 保険:医療・生命の最適化
重複保障や過剰保障を削れば、同じ安心をより低コストで確保できます。
通院保障特約は入院後の通院のみ対象が一般的です。条件を確認し、必要最小限で設計しましょう。
4. サブスク:統合と解約
映像・音楽・クラウドを用途別に洗い出し、重複を統合します。
年払いへ変更や家族共有でコスパ向上を狙い、使わない月は一時停止を活用します。
5. 住居費:住宅ローン見直し
金利差と残期間次第で、借り換えにより総返済額を大きく圧縮できます。
諸費用と手間を上回る効果が出るか、試算ツールで損益分岐点を確認しましょう。
注意ポイント
見直しは「固定費→変動費→収入アップ」の順が効率的です。毎月の自動積立を同時に設定し、削減効果を消費に戻さない仕組み化が肝心です。
保険の最適化|医療保険・生命保険・変額保険の賢い使い分け
家計を守りつつ将来の資産形成につなげるには、役割ごとに商品を分けるのが基本です。
医療費リスク、死亡保障、長期の増やすお金を切り分けると、ムダなコストを抑えられます。
1. 医療保険:入院中心+必要特約のみ
入院給付金を基軸に設計し、先進医療や三大疾病などは優先度で選びます。
通院保障特約は入院後の通院のみ対象が多いため、外来中心の想定なら無理に付けない選択も有効です。
2. 生命保険:必要保障額から逆算
教育費・生活費・住宅ローン残高を踏まえ、期間限定なら定期保険で低コストに。
終身保障が必要かは、老後の収支や資産規模に照らして判断しましょう。
3. 変額保険:長期の資産形成で活用
運用成果で解約返戻金が変動するため、長期積立と分散を前提にします。
老後資金を目的に、家計余剰から計画的に積み立てると、インフレ耐性のある資産形成が狙えます。
通信・サブスクの圧縮術|品質を落とさずコスパを上げる
速度・容量・使い方を数値化すれば、最適プランは自動的に絞れます。
家族内でデータシェアやアカウント共有を行い、重複契約を削除しましょう。
ここに注目!
年間コストで比較し、初年度割・違約金・端末残債まで含めた「総支払額」で意思決定しましょう。
住居・車の固定費を減らす5アクション
住居・車は金額が大きく、意思決定の一回で家計インパクトが長期に及びます。
借り換えや保険の見直し、保有形態の変更まで検討すると、削減余地が広がります。
1. 住宅ローンの借り換え
固定・変動の組み替えや金利差で、総返済額を圧縮できます。
手数料や保証料を含め、3〜5年で回収できるかを目安に判断します。
2. 火災・地震保険の再設計
補償の重複を削り、免責を調整すると保険料が下がります。
耐震等級や見直し時期のキャンペーンも確認しましょう。
3. 自動車保険の補償調整
走行距離・年齢条件・車両保険の方式で料率は大きく変わります。
特約は必要最小限にし、ドラレコ割引なども比較します。
4. カーシェア・サブスク検討
利用頻度が低いなら保有より利用の方が総額で安くなります。
通勤・買物の実利用データを1か月記録して判断しましょう。
5. メンテ費と駐車場の最適化
タイヤ・保険・税金の更新月をカレンダー管理し、相見積もりを徹底します。
駐車場は距離と価格のトレードオフで最適化しましょう。
固定費見直しの実行ステップ|3日で終える進め方
家計簿アプリで明細を自動取得し、重複・未使用・割高の3観点で丸ごと棚卸しします。
意思決定は「いま解約」「次回更新で変更」「保留」の三分類で即断即決が鉄則です。
| 特徴 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 格安SIMへの移行 | 月額数千円の恒久削減 | 回線品質とサポートの確認が必要 |
| 保険の再設計 | 重複排除で家計最適化 | 通院特約の適用条件を要確認 |
| 変額保険で積立 | インフレ耐性の資産形成 | 元本変動リスクを理解して長期運用 |
インタビュー|FPに聞く!固定費見直しで家計はどう変わる?

34歳・女性
見直すといいと聞きますが、保険や通信などは「面倒で後回し」にしてしまいがちです。
スマホdeほけん
その気持ち、よく分かります。ですが固定費は一度変えるだけで“ずっと節約できる”のが強み。努力を続けなくても成果が継続しますよ。
34歳・女性
見直しでどれくらい家計が変わりますか?
スマホdeほけん
通信・保険・サブスクの3つだけでも月1〜2万円の改善は現実的です。その分、老後資金や投資にまわせます。
34歳・女性
保険を見直すと保障が薄くなるのが不安です。
スマホdeほけん
そこは「必要な保障は残し、ムダを削る」設計で対処できます。通院特約や終身保険の見直しが効果的ですね。
34歳・女性
どの順番で取り組むとスムーズですか?
スマホdeほけん
まずは「明細が確認しやすい通信・サブスク」→「支払いが大きい保険・住宅費」と段階を踏めばストレスが少なくて済みますよ。
Q&A:固定費見直しでよくある疑問

Q1. まず何から手を付ければいい?
A. 金額インパクトが大きい通信・保険・住居の順がおすすめです。家計簿アプリで契約と金額を見える化してから着手しましょう。
Q2. 医療保険の通院保障は外来だけでも出ますか?
A. 多くは入院後の通院のみ対象です。外来のみの治療を想定するなら、特約の有無と条件を必ず確認してください。
Q3. 見直しで保障が薄くなるのが不安です。
A. 必要保障額を算出し、優先度の低い特約から削れば安心は維持できます。専門家相談でダブルチェックすると安全です。
Q4. 変額保険はリスクが怖いのですが?
A. 長期・分散・積立を前提にすれば価格変動の影響は平準化されます。目的と期間を決め、無理のない金額で始めましょう。
Q5. 削減したお金はどう使うべき?
A. まずは生活防衛資金、次に老後資金と教育費の積立に回します。自動積立にして消費へ戻らない工夫をしましょう。
まとめ:固定費を削って未来の自分へ投資する
固定費の見直しは、努力を継続しなくても効果が積み上がる家計術です。通信・保険・住居を順番に整えるだけで、毎月のキャッシュフローは改善します。
浮いたお金を老後資金や資産形成へ回し、変額保険など長期の仕組みで増やす設計に変えましょう。迷ったら専門家に相談し、最短ルートで成果を出してください。
外部リンク|家計管理と保険見直しに役立つ公的情報源
中立的な立場で信頼できる情報を提供する公的機関のサイトを紹介します。見直しの判断に迷った時は、まずここから確認を。
| サイト名 | 概要 |
|---|---|
| 金融庁 | 保険や金融商品の仕組みと注意点を解説 |
| 内閣官房「家計の見える化」 | 生活コスト削減のための公的資料を掲載 |
| 全国健康保険協会 | 医療費・高額療養費制度の仕組みを案内 |
| 厚生労働省 | 社会保障・医療制度の全体像を解説 |
監修者からひとこと




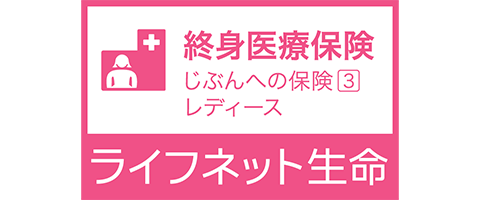
スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
固定費の見直しは、家計改善とリスク管理を同時に進める実務です。通信・保険・住居の優先順位を守り、契約更新月と特約条件を丁寧に確認しましょう。
医療保険の通院特約は入院後通院が中心である点に留意し、過不足のない保障へ再設計を。削減分は生活防衛資金と老後資金へ自動積立し、変額保険など長期商品は目的・期間・許容リスクを明確にして活用してください。