

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
保有資格
AFP・2級FP技能士
専門分野・得意分野
生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。
卵管閉塞は不妊の原因となる代表的な婦人科疾患のひとつです。特に30代以降の女性では発症率が高く、早期の発見と治療が妊娠への近道になります。
この記事では、卵管閉塞の基礎知識から、医療保険の保障内容、女性が押さえるべき保険の選び方まで徹底解説します。
卵管閉塞の原因と症状
卵管閉塞は、性感染症(クラミジア感染など)や過去の手術・炎症が原因で卵管が狭くなる、または詰まる疾患です。
無症状のまま進行することも多く、不妊検査で初めて発見されるケースが一般的です。
検査と治療内容、かかる医療費
卵管造影検査や腹腔鏡検査で診断され、閉塞が確認された場合は手術(癒着剥離や卵管形成術)が行われます。
治療費は手術や入院を伴うと保険適用でも10〜30万円程度かかる場合があります。
費用が高額になりがち
不妊治療と重なるケースでは、検査や処置が自由診療扱いとなり、さらに高額になることもあります。
医療保険選びのポイント
1. 通院保障の有無
卵管閉塞の治療では通院が中心になることが多いため、通院給付金が支給されるかが重要です。
特に検査や術後の経過観察もカバーできるか確認しましょう。
2. 女性特有疾病への対応
女性疾病特約が付帯されていれば、卵管閉塞も保障範囲に含まれる場合があります。
特約の保障内容と給付倍率に注目しましょう。
3. 手術給付金の条件
腹腔鏡や開腹手術が対象になるか、公的医療保険に連動する給付条件を確認しましょう。
自由診療扱いになると保障外になるケースもあるため注意が必要です。
4. 既往歴告知の影響
過去に卵管閉塞の治療歴がある場合、保障対象外となることもあります。
正確な告知を行い、加入前に引受基準緩和型保険も検討しましょう。
5. 不妊治療との関連性
体外受精などの不妊治療は多くが保険適用外ですが、卵管閉塞の治療が前提の場合は保険が適用されることもあります。
医療機関での診断書取得や保険会社への確認が必要です。
Q&A:卵管閉塞と医療保険に関するよくある質問
Q1. 卵管閉塞でも医療保険に加入できますか?
A. 治療完了後であれば加入できる場合がありますが、制限付きや部位不担保となることもあります。
Q2. 卵管造影検査は医療保険の対象ですか?
A. 検査目的によります。診断目的なら保険適用ですが、不妊治療の一環とみなされると対象外になることもあります。
Q3. 再発した場合も保障されますか?
A. 保険により異なりますが、再発が既往歴と見なされることもあるため、契約内容を確認してください。
Q4. 保険金の請求には診断書が必要ですか?
A. 原則として医師の診断書が必要です。検査内容や手術歴を記載してもらいましょう。
Q5. 女性特約は必要ですか?
A. 卵管閉塞を含む婦人科系疾患に手厚い保障が欲しい場合は、女性特約の加入をおすすめします。
まとめ
卵管閉塞は不妊の原因として女性に大きな影響を与える疾患ですが、医療保険の備えによって安心感を得ることができます。
検査・通院・手術など各段階に応じた保障が整っている保険を選ぶことが重要です。
監修者からひとこと




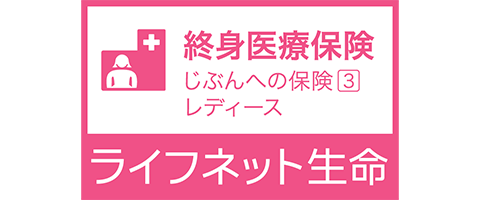
スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
卵管閉塞は、不妊症の原因の中でも比較的頻度が高く、特に若年層の女性でも発症する可能性がある疾患です。性感染症(クラミジア感染症など)や骨盤内炎症性疾患(PID)、過去の開腹手術や子宮内膜症の影響などが閉塞の要因となることがあります。
このような卵管障害は、症状が軽微または無症状で進行することが多く、発見が遅れることで不妊治療の開始時期も遅れがちになるため、早期診断・早期対応が重要です。卵管造影検査や通水検査などを通じて適切に診断し、必要に応じて体外受精(IVF)などの高度生殖医療に移行するケースもあります。
医療保険を検討する際には、手術や入院といった治療費だけでなく、再発や再治療に備えた長期的な視点が重要です。また、特定の治療歴が告知対象となることがあるため、妊娠を希望する前段階での加入が望ましいといえるでしょう。