

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
保有資格
AFP・2級FP技能士
専門分野・得意分野
生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。
「うつ病になったら保険には入れないの?」と不安を感じていませんか。うつ病と保険加入の関係は複雑で、誤った情報に惑わされる方も多いです。
この記事では、うつ病の人が加入できる保険の種類・加入のポイント・公的制度の活用方法をわかりやすく解説します。さらに、うつ病で保険金はおりるのか、告知義務違反のリスクも詳しく紹介。最後まで読めば、備え方が明確になります。
うつ病と保険加入の基本|なぜ加入が難しいのか?
うつ病を含む精神疾患は、一般の保険加入でハードルが高いと言われます。理由は、長期の治療や再発リスクがあり、保険会社が高リスクと判断するからです。
告知義務に「精神疾患」の項目が含まれている場合、治療中や過去の通院歴があると加入を断られる可能性があります。
この記事で解説する重要ポイント
1. なぜうつ病で保険加入が難しい?
うつ病は完治までに時間がかかり、再発率も高いため、保険会社にとってリスクが大きいと判断されます。結果として、一般的な医療保険・生命保険では審査が厳しくなります。
しかし、治療状況や経過次第では、加入できる保険もあります。
2. 加入しやすい保険の種類
うつ病や精神疾患があっても加入できる可能性が高いのは、引受基準緩和型保険や無選択型保険です。
これらは健康状態の告知項目が少なく、医師の診断書が不要な場合もありますが、保険料は割高になる傾向があります。
3. 保険金はおりる?注意点
うつ病による入院や通院は、保険の対象外になることが多いです。
ただし、うつ病が原因で発生した別の病気やケガは保障される場合があります。契約前に約款で対象外条件を必ず確認しましょう。
4. うつ病の人が使える公的制度
自立支援医療制度や傷病手当金など、うつ病の治療や休職中の生活を支える公的制度があります。
特に傷病手当金は、条件を満たせば給与の約2/3が最長1年6ヶ月支給されます。
5. 専門家が教える備え方
うつ病がある場合は、民間保険だけでなく公的制度や貯蓄も含めてトータルで備えることが重要です。
ファイナンシャルプランナーや保険ショップで、家計と健康状態に合った保障プランを相談するのがおすすめです。
うつ病でも入りやすい保険の種類
通常の保険に加入できない場合でも、選択肢はあります。ここでは、引受基準緩和型・無選択型・がん保険などを解説します。
加入検討できる保険タイプ
1. 通常の医療保険に入れるケース
うつ病と診断されても、治療が完了し、一定期間が経過していれば加入できることがあります。入院歴や再発リスクが審査のポイントです。
治療中や投薬中は難易度が高いため、状況に応じて別の選択肢を検討しましょう。
2. 引受基準緩和型の医療保険
告知項目が少なく、過去の病歴に対する基準が緩い保険です。うつ病のある方でも加入しやすいのが特徴です。
ただし、保険料は割高で、加入後1年以内の保障制限があります。
3. 無選択型(無告知型)保険
健康状態の告知が不要で、診査もありません。加入ハードルは最も低いですが、保険料負担が大きいため、最終手段と考えましょう。
4. がん保険
がんの告知のみを問うため、うつ病があっても加入できる可能性があります。ただし、がん以外は保障対象外なので注意してください。
5. 収入保障保険(条件付き)
一定の条件を満たせば、うつ病があっても収入保障保険に加入できる場合があります。
ただし、精神疾患による就業不能は保障対象外となることが多いため、約款を必ず確認しましょう。
うつ病で保険金はおりる?加入後の注意点
うつ病発症後の保険利用は条件付きです。特に、告知義務違反には要注意。告知を隠すと、保険金が支払われないどころか契約解除されるリスクもあります。
| ケース | 給付対象 | 注意点 |
|---|---|---|
| 加入後にうつ病で入院 | 医療保険なら給付対象 | 免責期間や上限に注意 |
| 就業不能保険 | 商品により対象外も多い | 精神疾患特約の有無確認 |
| 無選択型保険 | 加入後1年は保障制限 | 保険料が割高 |
よくある質問(Q&A)

Q1. うつ病で通常の保険に加入できないのはなぜ?
A. 再発や長期治療のリスクが高く、保険会社が慎重に審査するためです。
Q2. うつ病を隠して加入したらバレますか?
A. ほぼ確実にバレます。保険金請求時に過去の診療情報が調査されます。
Q3. 加入後にうつ病になった場合、給付金はおりる?
A. 医療保険での入院給付は対象ですが、免責期間や条件を確認しましょう。
Q4. うつ病でもがん保険に入れる?
A. がんに関する告知のみなので、加入できる可能性があります。
Q5. 公的制度はどれを利用すべき?
A. 傷病手当金と障害年金、自立支援医療の3つは特に重要です。
まとめ
うつ病で一般的な保険加入は難しいですが、引受基準緩和型や無選択型など選択肢はあります。さらに、傷病手当金や障害年金といった公的制度を組み合わせることで、経済的リスクを減らせます。
「うつ病だから保険は無理」と諦めず、早めに情報収集と相談を行いましょう。
うつ病の人が利用できる公的制度と窓口
保険に入れない場合も、国の制度で支援が受けられます。以下の制度を把握しておきましょう。
監修者からひとこと



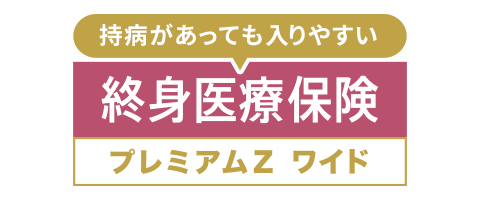

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
うつ病と保険は非常に複雑なテーマですが、備えは早いほど有利です。若いうちに加入すれば、リスクが低く保険料も抑えられます。症状がある方は、緩和型や無選択型を活用しつつ、公的制度の理解を深めましょう。専門家に相談することで、自分に最適な選択が見えてきます。