

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
保有資格
AFP・2級FP技能士
専門分野・得意分野
生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。
「もしものとき、家族にどれくらいの保障を残せば安心?」と悩んでいませんか。死亡保険は、のこされた家族の生活や教育資金を守る重要な役割を持ちます。
しかし、適正な保障額は家庭の状況によって異なります。本記事では、必要保障額の計算方法やケース別の目安を、専門家の視点でわかりやすく解説します。死亡保険選びに迷っている方は必見です。
死亡保険の種類と特徴を理解しよう
まずは、死亡保険の種類と特徴を押さえておきましょう。大きく分けて3つのタイプがあります。
それぞれの仕組みを理解することで、自分に合った保険を選びやすくなります。
1. 定期保険
保障期間を10年・20年など一定期間に設定するタイプです。掛け捨てのため貯蓄性はありませんが、低コストで大きな保障を準備できるメリットがあります。
子育て中や住宅ローンのある世帯に適しています。
2. 養老保険
期間満了時に満期保険金を受け取れるタイプで、死亡時には死亡保険金が支払われます。
貯蓄性がある一方で、保険料は定期保険より高額になります。
注意ポイント
養老保険は「保障+貯蓄」目的の人におすすめ。ただし返戻率や満期時期を確認しましょう。
必要な死亡保険額はいくら?計算方法と考え方
保障額を決める際は「必要保障額積み上げ方式」を使います。必要な支出を積み上げ、遺族年金や貯蓄などの収入を差し引いて算出します。
以下のステップで整理します。
必要保障額を決めるステップ
1. 末子独立までの生活費
現在の生活費の70%を目安に計算しましょう。例:生活費30万円なら約21万円が必要額です。
子どもが小さい場合、必要保障額は大きくなります。
2. 配偶者の老後生活費
子ども独立後は生活費の50%程度を目安とします。平均余命まで計算すると、数千万円規模になるケースもあります。
老後資金不足のリスクをカバーするためにも慎重な試算が必要です。
3. 教育費や葬儀費用
大学まで進学する場合、教育費は子ども1人あたり平均で約830万円かかります。
さらに葬儀費用は全国平均で約118万円とされ、まとまった一時的支出として計算に含める必要があります。
4. 遺族年金・貯蓄の確認
必要保障額から、公的保障である遺族年金や既存の預貯金・金融資産を差し引きます。
これにより、保険で補うべき実際の不足額が明確になります。
5. 不足額を保険でカバー
算出された不足額を保障額として設定し、定期保険や終身保険などで備えます。
家計負担とのバランスを意識し、必要最小限の保険料で効率的な保障を確保しましょう。
| 支出項目 | 目安額 | 備考 |
|---|---|---|
| 生活費 | 月21万円 | 末子独立まで |
| 老後費用 | 月15万円 | 平均余命まで |
| 教育費 | 830万円 | 大学まで想定 |
| 葬儀費用 | 118万円 | 全国平均 |
ケース別・必要保障額の目安
実際の家庭でどれくらいの保障額が必要になるのか、代表的なケースを紹介します。
公的年金や預貯金を考慮しながら不足額を保険で補うのが基本です。
【ケース1】子どもあり・専業主婦の妻
夫35歳・妻35歳・子ども3歳の家庭で夫が亡くなった場合、必要資金は約1億2,558万円。一方で公的年金・貯蓄で7,132万円をカバーできます。
不足額は約5,400万円。この分を死亡保険で備えるのが理想です。
【ケース2】子どもなし・妻も働いている場合
共働きなら、妻の収入や遺族年金でカバーできる割合が大きく、不足額はほぼゼロに近いケースもあります。
この場合、葬儀費用や老後準備を目的に、終身保険で数百万円程度を確保すれば十分です。
ポイント
子どもの有無、住宅ローン、配偶者の就労状況で必要保障額は大きく変わります。
死亡保険加入時の注意点
保障額を決めたら、保険を選ぶ際の注意点も確認しましょう。
・目的に合った保険を選ぶ(定期保険 or 終身保険)
・過剰保障にならないよう定期的に見直す
・家計とのバランスを考慮する
| 保険タイプ | 特徴 | 適する人 |
|---|---|---|
| 定期保険 | 低コストで大きな保障 | 子育て世帯 |
| 終身保険 | 一生涯保障+貯蓄性 | 葬儀費用や老後資産目的 |
| 養老保険 | 満期時に保険金 | 保障+積立目的 |
FPに聞く!必要保障額と公的制度のリアル
実際に必要保障額を計算するとき、どこから手を付ければよいのか迷う声が多く寄せられます。
家計や老後資金、傷病手当金と民間保険の使い分けについて、FPが分かりやすく回答します。

34歳・女性
必要保障額は最初にどう見積もればよいですか?
スマホdeほけん
まず「末子独立までの生活費」「教育費」「配偶者の老後費」を積み上げます。次に公的年金や貯蓄、退職金見込みを差し引き、残りを保険で補います。


34歳・女性
共働き夫婦の場合、死亡保険は少なくても大丈夫ですか?
スマホdeほけん
配偶者の収入と遺族年金で不足が小さければ、保険金額は抑えられます。ただし住宅ローンや子どもの年齢次第で必要額は変動するため、試算は必須です。


34歳・女性
病気やケガで働けない期間は、死亡保険ではカバーできませんよね?
スマホdeほけん
はい。収入減には「傷病手当金」や就業不能保険を検討しましょう。死亡保障と生活費の補償は目的が異なるため、両輪で考えるのが合理的です。


34歳・女性
高額療養費制度があるなら、保険は最小でよいのでしょうか?
スマホdeほけん
医療費自己負担は抑えられますが、差額ベッド代や交通費、家計の固定費は対象外です。家族の生活維持を重視し、必要保障額から逆算しましょう。


34歳・女性
インフレや金利上昇は必要保障額に影響しますか?
スマホdeほけん
長期の生活費や教育費に影響します。試算は実質金利を意識し、3~5年ごとに見直すと過不足が防げます。保険料負担が重い場合は段階的な見直しも有効です。

Q&A:死亡保険に関するよくある質問

Q1. 死亡保険の必要保障額はどう計算しますか?
A. 家族の生活費や教育費、葬儀費用などの将来支出を積み上げ、遺族年金や貯蓄額を差し引きます。不足分を保険で補うのが基本です。
FP相談やシミュレーションツールを活用すると精度が高まります。
Q2. 共働き夫婦でも死亡保険は必要ですか?
A. 配偶者の収入が安定していれば必要額は減りますが、住宅ローンや将来の子どもの教育費を考慮すると一定の保障はあった方が安心です。
夫婦双方に収入減のリスクがある場合、保険で補填する価値は高いです。
Q3. 死亡保険は定期型と終身型のどちらがよいですか?
A. 定期型は低コストで大きな保障を確保でき、ライフステージに合わせやすいのが特徴です。終身型は一生涯保障と貯蓄性があります。
目的や家計状況に合わせて組み合わせるのも有効です。
Q4. 公的年金だけで生活できる場合、死亡保険は不要ですか?
A. 遺族年金や貯蓄で生活費が十分にまかなえる場合、加入は不要かもしれません。ただしインフレや予期せぬ支出に備えたい人は加入を検討します。
精神的な安心感を得る目的で少額加入する人もいます。
Q5. 死亡保険はいつ見直せばよいですか?
A. 子どもの誕生、住宅購入、退職などライフイベントがあったときが見直しのタイミングです。
3~5年ごとの定期点検で保障の過不足を防ぎ、家計負担を最適化できます。
まとめ
死亡保険の保障額は一律ではなく、家庭の状況で大きく変わります。必要額を試算し、公的保障や貯蓄を考慮したうえで不足分を保険で備えるのが基本です。
ライフステージに応じて見直すことも忘れず、家族の安心を守るプランを準備しましょう。
公的制度の公式情報で最新ルールを確認しよう
保険を決める前に、公的制度の内容と申請要件を把握しておくと、過不足のない保障設計につながります。
以下は信頼できる公的機関の公式ページです。必要保障額の試算と合わせて確認しましょう。
| 制度名 | 概要 | 公式リンク |
|---|---|---|
| 高額療養費制度 | 自己負担が上限を超えた分を払い戻し。食事代・差額ベッド代は対象外。 | 厚生労働省 |
| 傷病手当金 | 病気・ケガで就労不能時に給与の約3分の2を支給(通算1年6ヶ月)。 | 全国健康保険協会 |
| 遺族年金 | 遺族の生活を支える年金。対象や金額は家族構成・加入歴で変動。 | 日本年金機構 |
| 医療費の自己負担割合 | 年齢・所得区分で1~3割。高齢者や現役並み所得の扱いを確認。 | 厚生労働省 |
| 先進医療制度 | 先進医療は保険適用外で技術料は全額自己負担。対象療法は随時更新。 | 厚生労働省 |
監修者からひとこと


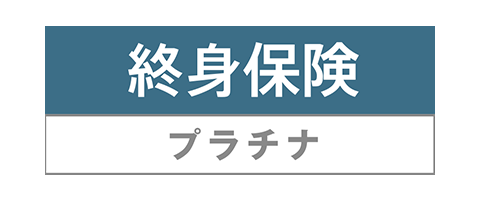
スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
死亡保険の加入検討では、まず「必要保障額」を正確に算出することが出発点です。これは遺族の生活費、教育費、老後資金など将来の支出見込みから、公的保障(遺族年金等)や既存の預貯金を差し引いて求めます。
そのうえで、残された期間の家計負担に耐えられる保険料設定を行うことが不可欠です。保障期間は子どもの独立や住宅ローン完済までに合わせるのが基本で、余裕資金があれば終身保険による葬儀費用や老後資産の準備も検討できます。市場金利やインフレ動向、将来の収入変動リスクも考慮し、定期的な見直しで過不足のない保障を維持してください。