

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
保有資格
AFP・2級FP技能士
専門分野・得意分野
生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。
「入院中でも入れる保険ってあるの?」と不安な方は多いでしょう。実際、通常の保険加入は難しいですが、例外として加入できるタイプも存在します。本記事では、加入可能な保険の種類や注意点、公的制度の活用方法を専門家がわかりやすく解説します。
入院費の自己負担を減らす方法や、収入減に備える手段も紹介しますので、最後までご覧ください。
入院中の保険加入はなぜ難しいのか
生命保険や医療保険に加入する際は、告知義務があります。現在入院中の方は、保険会社にとって給付金支払リスクが高いため、通常の加入はほぼ不可能です。
加入できても、今の入院や治療は対象外になる場合が多いので注意が必要です。
入院中でも加入可能な「無選択型保険」とは?
無選択型保険は、健康告知が不要なため、持病や過去の病歴があっても加入できます。しかし、入院中は加入不可のケースが多いため、事前確認が必須です。
加入できても、既往症や現在の病気に関しては保障対象外となります。
1. 告知なしで加入できる
一般的な医療保険とは異なり、健康状態を申告する必要がありません。
そのため、持病や過去の入院歴がある人でも加入できる可能性があります。
2. 持病や既往症もOK
無選択型保険では、持病や既往症があっても加入できます。
ただし、加入できても既往症に関する保障は対象外になるケースが多いので注意が必要です。
3. 入院中は加入不可のことが多い
「告知なし」とはいえ、現在入院中や入院予定がある場合は加入できない商品がほとんどです。
入院前に加入しておくことが重要です。
4. 保険料は割高
リスクを引き受ける分、無選択型保険は一般的な医療保険より保険料が高めに設定されています。
月額保険料が通常より数千円高くなる場合もありますので、費用対効果を検討しましょう。
5. 現在の病気は対象外
加入前から治療中の病気や入院に関しては、保障の対象外となります。
このため、加入直後に給付金を受け取れるケースはほとんどありません。
公的制度で入院費を減らす2つの方法
入院中は医療費や生活費がかさむため、公的制度を活用することが重要です。
ここでは「高額療養費制度」と「傷病手当金」を紹介します。
| 制度名 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 高額療養費制度 | 自己負担額を上限まで軽減 | 対象は医療費のみ |
| 傷病手当金 | 給与の約2/3を補償 | 自営業は対象外 |
| 医療費控除 | 確定申告で税金軽減 | 領収書の保管が必要 |
注意ポイント
公的制度は自己申請が必要で、申請しないと給付を受けられません。
公的制度に関する公式情報リンク集
入院費や医療費に関する正確な情報を確認するため、以下の公的機関サイトを参考にしてください。
| 機関名 | 概要 |
|---|---|
| 厚生労働省 | 医療制度・高額療養費制度の詳細を確認できます。 |
| 全国健康保険協会(協会けんぽ) | 高額療養費制度や傷病手当金の手続き方法を掲載。 |
| 国税庁 | 医療費控除の申請方法や必要書類の確認。 |
| 日本年金機構 | 公的年金や障害年金など、生活保障制度を解説。 |
| 国民健康保険連合会 | 国保加入者向けの高額療養費や給付制度を案内。 |
高額療養費制度の詳細と計算例
1ヶ月の医療費が一定額を超えると、超過分を払い戻してもらえる制度です。例えば、年収500万円で60万円の医療費がかかった場合、自己負担は約8.3万円に抑えられます。
申請方法や所得区分による上限額は事前に確認しましょう。
傷病手当金で収入減をカバー
傷病手当金は、働けなくなった場合に給与の2/3を最長1年6ヶ月受給できます。
ただし、対象は会社員・公務員で、自営業やフリーランスは対象外です。
ケーススタディ:入院中の保険と公的制度の活用例
実際にどのように保障を受けられるか、4つの事例で紹介します。
事例1:無選択型保険に加入できたケース
入院中では加入不可だったが、退院後すぐ加入でき、今後の入院保障を確保。
事例2:高額療養費制度で医療費を軽減
60万円の医療費が8.3万円に軽減。差額ベッド代は自己負担。
事例3:傷病手当金で生活費を確保
給与の2/3が最長1年6ヶ月支給され、安心して療養できた。
事例4:保険加入できず公的制度をフル活用
保険に加入できなかったが、高額療養費制度と医療費控除で負担を軽減。
加入可能な保険の特徴まとめ
無選択型保険や引受基準緩和型保険など、加入しやすい商品があります。ただし、入院中は加入不可のケースが大半です。
重要ポイント
健康なうちに加入しておくことが最大のリスクヘッジです。
よくある質問(Q&A)

Q1. 入院中でも入れる保険はありますか?
A. 無選択型保険などがありますが、ほとんどは入院中は加入不可です。
Q2. 無選択型保険の注意点は?
A. 保険料が高く、現在の病気は対象外です。
Q3. 公的制度でどれくらい負担が減りますか?
A. 高額療養費制度で医療費は月8万円程度に抑えられます。
Q4. 自営業者は傷病手当金をもらえますか?
A. いいえ、対象外です。代わりに貯蓄や保険加入で備えましょう。
Q5. 保険加入のベストタイミングは?
A. 健康なうちに加入するのが理想です。
まとめ
入院中の保険加入はほぼ不可能で、無選択型保険も制約があります。そのため、公的制度をフル活用し、将来に備えて早めの保険加入を検討しましょう。
監修者からひとこと



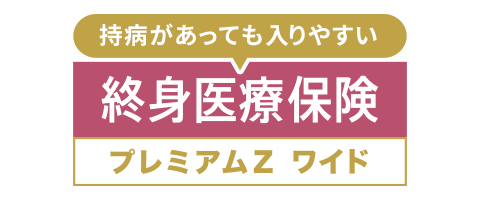

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
入院中に新たに保険に加入できる可能性は、実務上きわめて低いといえます。仮に加入できても、現在の入院や治療は保障対象外となるケースが大半です。そのため、入院費用や生活費のリスクを軽減するには、公的制度の活用と事前の備えが重要です。
具体的には、高額療養費制度で自己負担額を抑え、傷病手当金で収入減をカバーすることが基本となります。さらに、健康なうちに医療保険や収入保障保険を準備しておくことで、突発的なリスクから家計を守れます。保険と公的制度を組み合わせた総合的なリスクマネジメントが、安定した生活を維持する鍵です。