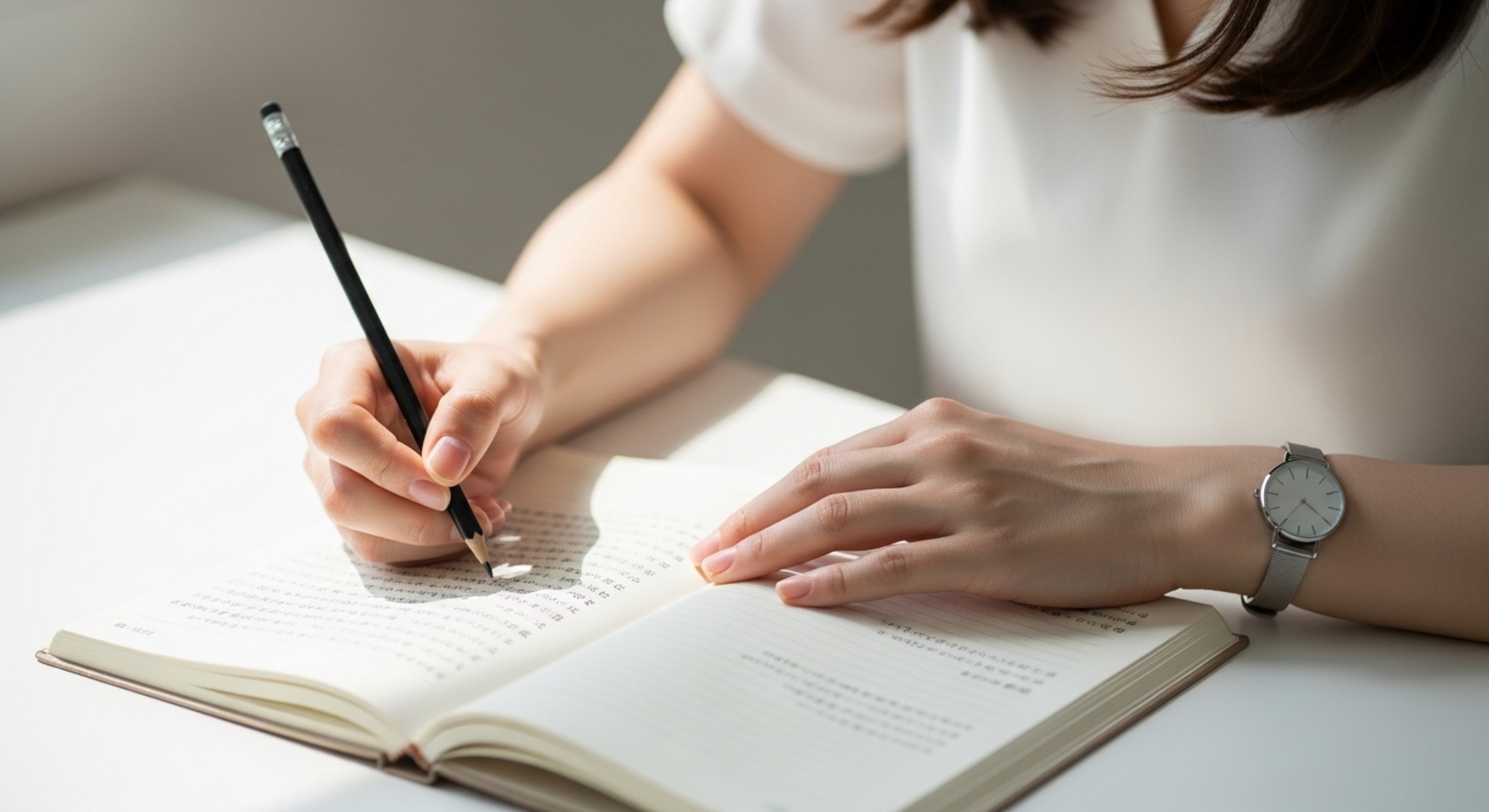

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
保有資格
AFP・2級FP技能士
専門分野・得意分野
生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。
骨壊死は血流の障害により骨の一部が壊死する病態で、大腿骨頭壊死などでは人工関節手術が必要になるケースもあります。慢性疾患であり、治療歴がある方は医療保険の加入にハードルを感じることも。
そこで選択肢となるのが「引受基準緩和型医療保険」。今回は骨壊死の概要から、保険加入のポイント、診査で問われやすい点を詳しく解説します。
骨壊死とは?主な原因と症状
骨壊死は「無菌性壊死」とも呼ばれ、外傷やステロイド投与、アルコールの多量摂取などが要因になります。血流が途絶えることで骨が死滅し、次第に痛みや可動域制限が生じます。
代表例として大腿骨頭壊死があり、歩行困難になることもあるため、MRIやCTでの早期診断が重要です。進行すれば人工関節置換術が選択されます。
医療保険加入に影響する要因は?
骨壊死は慢性的に治療を要するため、一般の医療保険では告知事項として厳しく評価される傾向があります。特に手術歴や通院の頻度がチェックポイントになります。
過去に人工関節手術を受けている場合や、症状が進行中の方は、通常の医療保険の診査が厳しくなることがあります。
注意ポイント
骨壊死の診断時期、治療法(保存療法/手術)、現時点での状態を正確に伝えることが重要です。
引受基準緩和型医療保険の特長
持病や治療歴がある方でも比較的加入しやすいのが、引受基準緩和型医療保険です。告知項目が限定され、骨壊死のような慢性疾患でも一定の条件下で加入可能な商品があります。
ただし、保険料が高めで給付制限があるため、加入前に保障内容の確認は必須です。
1. 診断からの経過年数
骨壊死と診断された時期は、加入診査に大きく影響します。数年経過して症状が安定している場合、加入できる可能性は高まります。
治療終了後2年以上経過しているかをチェックされるケースが多いです。
2. 手術歴の有無
人工関節手術の有無、入院期間などは重要な告知事項です。術後に良好な経過であれば、診査が通ることもあります。
手術から一定期間経過しているかがカギとなります。
3. 慢性疼痛の状況
慢性的な痛みが継続している場合、就労状況や通院頻度も確認されます。
通院治療が継続中か否かが重要な判断材料になります。
4. 給付制限と免責条件
加入後の一定期間は給付対象外になる「免責期間」が設定されていることがあります。
契約内容を確認し、どの疾患が給付対象外かを把握しておきましょう。
5. 他の疾患との併存
骨壊死は糖尿病やステロイド性疾患など他の病気と併存することがあります。
併存疾患の告知も忘れずに行いましょう。
| 項目 | 緩和型保険 | 通常の保険 |
|---|---|---|
| 加入条件 | 緩やか | 厳格 |
| 保険料 | やや高い | 割安 |
| 保障内容 | 限定的 | 広範囲 |
Q&A|骨壊死と医療保険の疑問

Q1. 手術をしていない場合でも加入できますか?
A. 保存療法のみで症状が安定していれば加入可能なケースがあります。
Q2. 完治証明は必要ですか?
A. 保険会社により異なりますが、診療明細や主治医の所見を求められることがあります。
Q3. 緩和型保険の保障は十分ですか?
A. 入院・手術に関する基本的な保障はありますが、がん・慢性疾患などは除外対象になる場合もあります。
Q4. 加入後に再発したら給付されますか?
A. 免責期間を過ぎていれば対象となる可能性があります。契約内容を確認しましょう。
Q5. 他の慢性病があると加入できませんか?
A. 商品により異なりますが、併存症が軽度なら加入できる場合もあります。
まとめ
骨壊死は治療や経過観察が長期に及ぶ疾患であり、医療保険への加入は慎重に行う必要があります。特に一般型保険では診査が厳しい傾向にあるため、持病を持つ方にとって「引受基準緩和型医療保険」は大きな選択肢となります。
正確な告知と自分の状態に合った商品選びで、将来の医療費に備えていきましょう。
監修者からひとこと


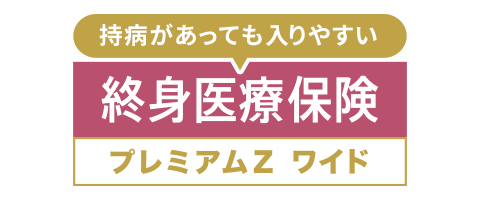

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
骨壊死は整形外科領域の中でも比較的難治性で、保存療法か手術かの選択は患者さんの生活様式にも影響します。こうした背景から、医療保険の診査では慎重な判断がされやすい疾患でもあります。
緩和型医療保険は、条件さえ満たせば加入が可能であり、手術費用や再発時の備えとして有効です。持病と上手く付き合いながら、保険でリスクに備えることが大切です。