

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
保有資格
AFP・2級FP技能士
専門分野・得意分野
生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。
月経前になると、心身の不調に悩まされる女性は少なくありません。月経前症候群(PMS)は、特に20代後半から40代の女性に多く見られる身近な疾患です。
気分の浮き沈みや身体の痛みに加えて、仕事や家事、育児にも影響を及ぼすことから、医療保険での備えを検討する方も増えています。
本記事では、PMSの基礎知識から治療内容、医療保険の保障範囲、保険加入時の注意点まで詳しく解説します。
月経前症候群(PMS)とは?
PMSは、月経の3〜10日前から始まる心身の不調の総称で、排卵後から月経開始までの間に起こります。
症状は200種類以上とも言われ、代表的なものには以下のようなものがあります。
主なPMSの症状
・情緒不安定、不安感、イライラ
・頭痛、腹痛、乳房の張り
・眠気、集中力の低下、倦怠感
・むくみ、食欲増加 など
厚生労働省の調査によると、女性の約70〜80%が月経前に何らかの不快症状を経験しており、そのうち約5〜8%が日常生活に支障をきたす重度のPMSとされています。
医療保険でPMSは保障される?
PMSは通院で治療されることが多いため、通院給付金の対象になるかがポイントです。
また、女性疾病特約の対象に含まれる保険商品もあるため、保障内容を事前に確認しましょう。
1. PMSで通院給付を受けるには?
医療機関を受診し、診断名がカルテに記載されていれば、通院給付金の対象となる可能性があります。
ただし、「日常的な症状」と見なされると給付対象外になる場合もあるため、診断書の内容が重要です。
2. 女性疾病特約の対象かどうか
PMSは女性ホルモンの変動によって引き起こされるため、女性特有の疾病として特約の対象になることがあります。
保険会社によって対象範囲が異なるため、商品比較が大切です。
3. 精神科通院・投薬と保険の扱い
PMSが重度でPMDD(月経前不快気分障害)と診断される場合、精神疾患の分類となり、精神科での治療が必要になることもあります。
この場合、精神疾患を対象外とする保険商品では給付が受けられないことがあるため注意しましょう。
4. PMSが告知義務の対象となるケース
継続的に治療を受けていたり、投薬治療歴がある場合には、保険加入時の告知義務が発生します。
症状が軽度で通院歴がない場合は、告知不要とされることもあります。
5. 加入時の注意点と保障の選び方
PMSに限らず、女性のライフスタイルに沿った保険選びが重要です。
通院保障・女性疾病特約を組み合わせ、再発リスクや精神面も考慮した設計が理想的です。
Q&A:月経前症候群と医療保険の疑問

Q1. PMSだけで保険給付を受けられますか?
A. 医療機関での診断・治療が前提です。自己判断では給付対象外となります。
Q2. 保険加入後にPMSと診断されたらどうなりますか?
A. 契約後であれば、保障の対象となります。継続的治療が必要な場合も安心です。
Q3. PMSの診断はどの診療科を受診すればよい?
A. 婦人科または精神科が一般的です。症状の内容に応じて選びましょう。
Q4. 精神科でのPMS治療も保障対象ですか?
A. 一部の保険では精神科治療を除外している場合があります。契約内容を事前に確認しましょう。
Q5. PMSはどのくらいの人が悩んでいるの?
A. 約70〜80%の女性が何らかのPMS症状を経験しており、重症例(PMDD)は5〜8%とされています。
まとめ
月経前症候群(PMS)は多くの女性に影響を与える疾患であり、医療保険での備えが心強い支えとなります。
通院保障や女性疾病特約の有無を確認し、自分に合った保険を選びましょう。
監修者からひとこと




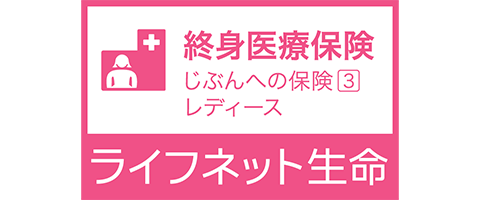
スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
PMS(月経前症候群)は、排卵後から月経開始前までの黄体期に生じるホルモンバランスの変動によって引き起こされる身体的・精神的症状の総称です。具体的には、情緒不安定・抑うつ・過敏・頭痛・乳房の張り・むくみ・倦怠感など、多岐にわたる症状が現れることがあり、生活の質(QOL)に大きな影響を及ぼすケースも少なくありません。
こうした症状が強く現れる場合、専門医による診断と治療が重要になります。近年では、低用量ピルやホルモン療法、漢方薬、カウンセリングなど多様な治療法が選択肢として存在しますが、継続的な通院や医療費が負担となることもあります。
医療保険を活用することで、PMSに伴う通院や検査、治療費の一部をカバーできる可能性があり、経済的負担を軽減しつつ、早期の受診と継続的なケアを受けやすくなります。とくに女性疾病に特化した保障内容を含む保険商品を選ぶことで、より実態に即した安心を確保することができます。自身のライフステージや症状の重さに応じて、専門家と相談しながら適切な保障内容を検討することが重要です。