

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
保有資格
AFP・2級FP技能士
専門分野・得意分野
生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。
妊娠・出産には喜びとともに、経済的な不安もつきものです。
健診費や分娩費用、入院費などが高額になることもあり、「助成制度って使えるの?」「何を申請すればいいの?」と悩む方も少なくありません。この記事では、妊産婦向けの医療費助成制度とその活用法を詳しく解説します。
妊娠・出産にかかる医療費の目安
分娩は基本的に保険適用外で、出産費用全体は平均40〜60万円程度とされています。
これに加えて妊婦健診費、異常分娩・帝王切開・入院費などでさらに負担が増すケースもあります。
| 項目 | 費用の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 正常分娩 | 約40〜50万円 | 保険適用外 |
| 妊婦健診 | 約10〜15万円 | 平均14回前後 |
| 帝王切開 | 約10〜20万円 | 保険適用あり |
| 入院費 | 1日1.5〜2万円 | 差額ベッド代含む |
妊産婦が利用できる主な医療費助成制度
公的制度を活用すれば、多くの医療費を軽減できます。
住んでいる自治体によって内容が異なるため、事前確認が重要です。
妊産婦向けの医療費助成制度一覧
1. 妊婦健診の費用助成
市区町村から交付される「妊婦健診受診票」により、14回分程度の健診費が助成されます。
自己負担は少なく済むよう配慮されています。
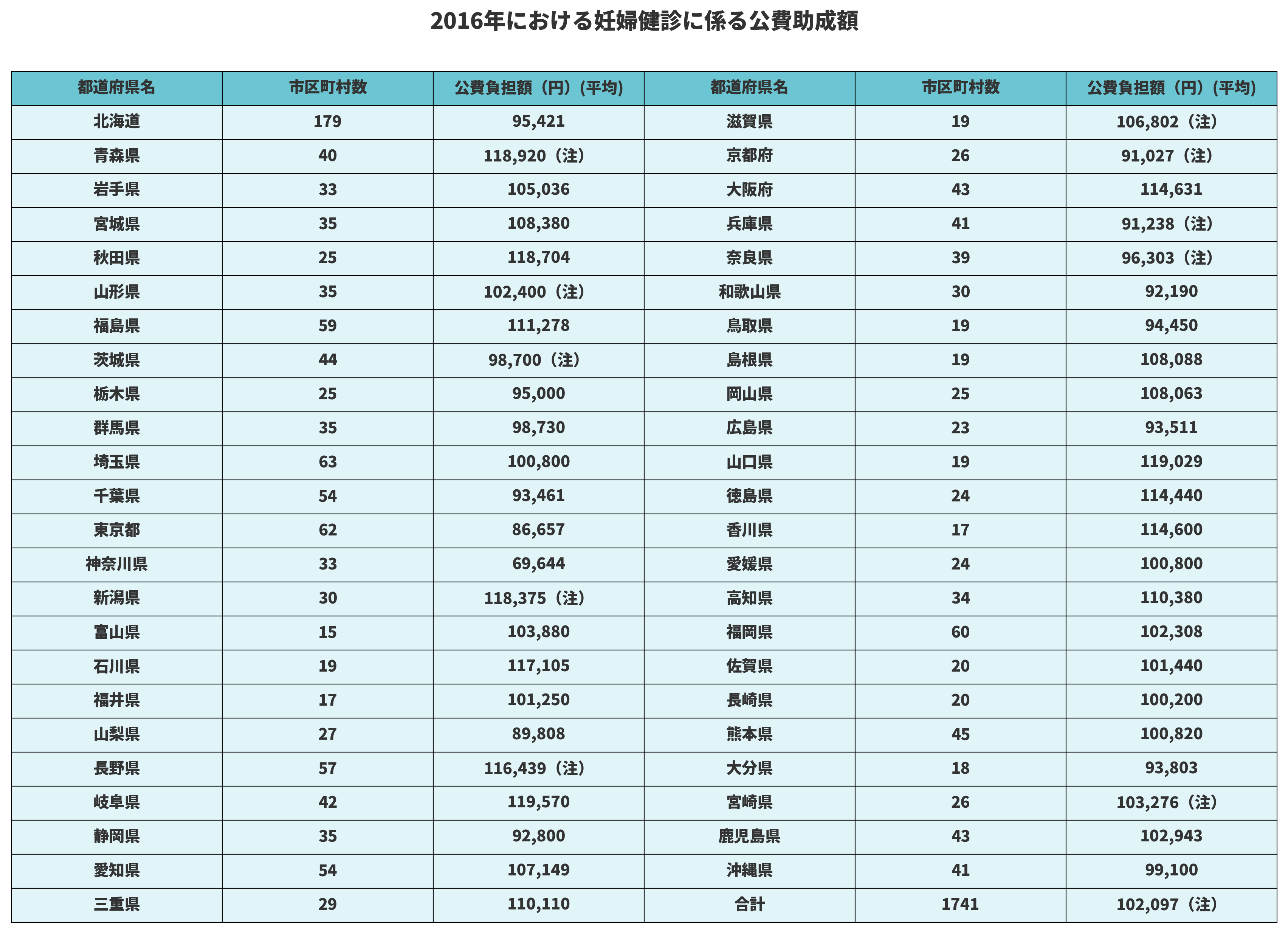
この表のとおり、妊婦健診に対する公費助成額は自治体によって大きく異なります。自身の住む自治体の金額を確認しておくと安心です。
2. 出産育児一時金
健康保険に加入していれば、子ども1人あたり原則50万円が支給されます(令和5年4月以降)。
医療機関に直接支払う「直接支払制度」も選べます。
注意ポイント
加入している健康保険組合によって支給額・手続き方法が異なる場合があります。
3. 高額療養費制度(異常分娩)
帝王切開や妊娠高血圧症候群などで入院・手術を受けた場合、健康保険適用+高額療養費制度の対象になります。
事前に「限度額適用認定証」を申請しておくと窓口負担が軽減されます。
4. 医療費控除(確定申告)
妊娠・出産に関連した通院費や医療費の合計が年間10万円を超えると、医療費控除の対象になります。
交通費や市販薬なども一部計上可能です。
5. 自治体の出産・入院費補助制度
一部の自治体では、入院・分娩費用の一部を助成する制度があります。
例:東京都港区「出産費用助成」最大10万円、名古屋市「出産支援給付金」など。
保険と助成制度の違いと併用のポイント
助成制度は自己負担の軽減、民間の医療保険は給付金による補填です。
帝王切開や異常妊娠に備えるには、女性向け医療保険が有効です。
Q&A|妊産婦の医療費助成制度に関する疑問
Q1. 妊婦健診の費用はすべて無料ですか?
A. 無料ではありませんが、受診票によって多くの費用が助成されます。自治体により上限が異なります。
Q2. 出産育児一時金はいつもらえる?
A. 分娩後、申請すれば1〜2ヶ月以内に支給されます。「直接支払制度」を使うと自己負担が抑えられます。
Q3. 帝王切開は保険適用されますか?
A. はい、帝王切開は医療行為として健康保険が適用されます。高額療養費制度も利用可能です。
Q4. 医療費控除はどの費用が対象?
A. 妊娠検査、健診、分娩費、通院交通費などが対象となります。領収書の保管を忘れずに。
Q5. 民間の医療保険は加入すべき?
A. 妊娠前に加入していれば、異常妊娠や帝王切開で給付金が受け取れる場合があります。
まとめ|妊娠・出産に備えて制度と保険を上手に活用しよう
妊娠・出産には予想外の出費がつきものですが、助成制度や保険を活用すれば家計負担は大きく軽減できます。
制度は自治体ごとに異なるため、妊娠がわかったら早めに確認・申請しておくのが安心です。
監修者からひとこと



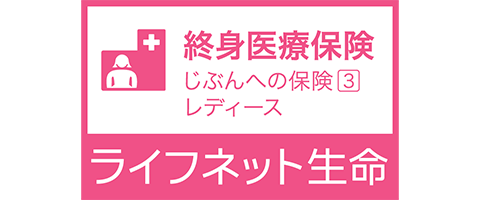
スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
出産は「健康保険が使えない医療行為」も多く、費用が高額になりやすい分野です。妊娠前から保険や制度を活用する視点が大切です。
助成制度と医療保険を併用すれば、安心して妊娠・出産期を迎えられる体制が整います。