

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
保有資格
AFP・2級FP技能士
専門分野・得意分野
生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。
「主婦の年金って本当に必要?」「将来、年金だけで老後は大丈夫?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。本記事では、主婦の年金制度の仕組みと「いらない」と言われる理由、そして実際に必要なケースについて詳しく解説します。これを読むことで、家計と老後資金の両面から合理的な判断ができるようになります。保険相談やweb完結型保険への意識づけにも役立つ内容です。
主婦の年金がいらないと言われる理由と背景
主婦の年金が「いらない」と考えられる背景には、制度的な優遇措置と誤解が混在しています。
第3号被保険者制度による保障
専業主婦やパート勤務の配偶者(収入が一定以下)は、第3号被保険者として国民年金の保険料が免除される制度があります。このため、自ら年金保険料を支払う必要がなく、最低限の年金受給権が確保されています。
自分で払っていない=もらえない」という誤解
一部では「保険料を支払っていないから年金は受け取れない」との誤解がありますが、第3号被保険者期間も将来の年金受給額に反映されます。
夫の厚生年金への依存
夫の厚生年金によって家計を支える前提の家庭が多く、あえて追加の個人年金やiDeCoへの加入を避けるケースも見られます。
ケース別具体例
・30代共働き夫婦:妻が年収103万円未満のため第3号被保険者
・50代専業主婦:長年第3号被保険者として加入し、追加の年金対策を行わず
それでも主婦の年金が必要なケースと判断の軸
主婦でも年金対策が重要となるケースと、その判断基準について解説します。
夫婦の収入減・離婚・死別リスク
夫の収入減や離婚・死別などにより、主婦が自力で老後資金を確保する必要に迫られる場合があります。このようなリスクに備えた準備は不可欠です。
公的年金だけでは不足する老後資金
老後の生活費と医療・介護費用を考慮すると、公的年金だけで十分な生活を維持するのは難しいケースが多いです。iDeCoやNISAの活用で自助努力が求められます。
判断軸としては、以下のポイントが挙げられます。
主婦の年金対策が必要な3つの状況
1. 夫婦いずれかが自営業やフリーランス
自営業やフリーランスの夫婦は第3号被保険者制度の対象外となり、自助努力による老後資金作りが必須です。
2. 夫婦の年収合算が将来減少する見込み
将来のリストラや転職によって収入減の可能性がある場合、主婦自身の年金準備が重要です。
3. 長寿リスクに備えたい場合
女性は平均寿命が長いため、長生きリスクに備えて追加の年金対策が合理的です。
主婦の年金にiDeCoは有効?
公的年金に上乗せできる制度として、iDeCoは節税効果と老後資金作りの両面で有効です。
Q&A|主婦の年金に関するよくある質問
Q1. 第3号被保険者はいつまで続く?
A. 配偶者が厚生年金に加入し、かつ自身の収入が一定額未満であれば継続します。条件を超えると第1号または第2号に切り替わります。
Q2. 離婚後の年金はどうなる?
A. 離婚時に年金分割を請求することで、婚姻期間中の厚生年金記録を分け合うことが可能です。
Q3. 専業主婦でもiDeCoに加入できる?
A. 第3号被保険者や自営業者(第1号被保険者)であればiDeCoに加入可能です。
Q4. 主婦の年金額はどのくらい?
A. 国民年金(老齢基礎年金)の満額で月額約6万6000円(2025年度見込み)です。
Q5. 年金以外に必要な老後資金の目安は?
A. 平均的な夫婦で2000万円程度の追加資金が必要とされていますが、家計状況により変動します。
まとめ
主婦の年金は「いらない」と誤解されがちですが、制度の正しい理解と将来リスクへの備えが不可欠です。家計やライフプランに応じてiDeCoやNISAの活用を検討し、十分な老後資金を確保することが安心な暮らしにつながります。
監修者からひとこと


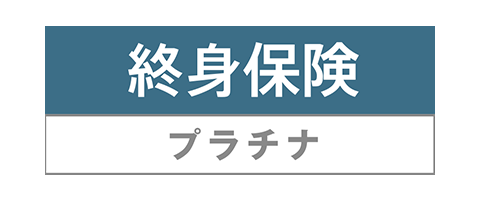
スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
年金制度は複雑で誤解が生じやすい分野です。特に主婦の年金は家族構成や就労状況により大きく異なります。将来の不安に備え、保険や資産形成を組み合わせたプランニングを行うことが賢明です。正しい知識と早めの準備が家計の安定と安心をもたらします。