

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
保有資格
AFP・2級FP技能士
専門分野・得意分野
生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。
「65歳から生命保険は必要?」と悩む声は多く、年金や貯蓄、健康状態で最適解は変わります。
公的保障と民間保険の役割分担を整理し、家計に無理なく老後資金を守る設計をやさしく解説します。
結論と全体戦略:迷わない判断軸と優先順位
65歳以降は「万一の費用」「医療・介護の自己負担」「遺族の生活差額」に分け、必要額だけを保険で補います。
まずは公的制度と貯蓄力を点検し、不足分を安価な保障で埋めるのがコスパ重視の王道です。
1. 遺族の生活費と葬儀費の見える化
配偶者の生活費と葬儀・整理費用を合算し、必要保障額を算出します。過大な死亡保障は家計を圧迫します。
目標額を数値で固定すれば、終身・定期・葬儀保険の適正規模が素早く見えてきます。
2. 医療・介護の自己負担の把握
医療は高額療養費で平準化されますが、差額ベッドや交通費は自己負担です。介護は長期化で累積負担が増えます。
医療保険や介護保険の役割は、対象外費用と長期費用の平準化にあります。
3. 公的年金・高額療養費の確認
年金額と医療の自己負担上限を整理し、毎月のキャッシュフローを可視化します。認定証の活用も前提です。
制度で下支えされる分、民間の必要額は圧縮でき、無駄な保険料を削減できます。
4. 貯蓄と流動資金の余力確認
生活防衛資金の確保状況を確認し、突発費用に即応できるかを点検します。預貯金の換金性も重要です。
余力が厚い場合は保険を最小限にし、保険料を老後資産の維持に回します。
5. 保険料負担と費用対効果
高齢加入は保険料が上がるため、削れる保障は潔く絞ります。必要額に直結する特約だけを選定します。
浮いた保険料はつみたてや変額保険の長期積立に回し、将来の取り崩しリスクを下げましょう。
65歳から検討したい保険:タイプ別の賢い使い分け
役割が重複するとコスパが低下します。各タイプの「使いどころ」を明確化し、最小コストで備えます。
ここでは代表的な6カテゴリーを、優先順位の考え方とともに整理します。
死亡保険(定期・終身)の基本設計
遺族生活費と葬儀費用が中心。子の独立後は大口保障は不要になり、終身は規模を絞るのが現実的です。
定期は安価ですが更新で保険料増。終身は高めでも一生涯保障と解約返戻金が特徴です。
医療保険:対象外費用の平準化
差額ベッドや交通など現金支出を想定し、入院一時金や短期入院に強い設計を検討します。
貯蓄が厚いなら日額を薄く、一時金中心にミニマム構成にする選択も現実的です。
がん保険:長期治療リスクへの備え
初期一時金と通院・再発に着目し、自由治療の自己負担も想定します。保障重複の点検が重要です。
既往のある場合は引受基準緩和型の選択肢も確認しましょう。
介護保険:長生きリスクの本丸
要介護認定時の一時金や年金型で、在宅・施設の自己負担を平準化します。長期化に備える発想です。
公的介護保険の限度を踏まえ、民間での上乗せ範囲を明確にします。
葬儀保険(終活向けの少額保障)
加入年齢が広く、健康に不安があっても入りやすい商品が多めです。過大加入は避けましょう。
葬儀形式の希望と相続の手続費まで含め、必要額を固めると無駄が減ります。
個人年金・変額保険:老後資金の補強
不足分の底上げに役立ちます。確定年金は受取期間が明確、変額保険は資産形成と保障の両立が魅力です。
価格変動リスクは分散と長期で抑え、取り崩し開始時期から逆算して設計します。
持病があっても入りやすい選択肢:告知でつまずかない
健康不安で一般型が難しい場合も、緩和型や無選択型で選択肢が広がります。条件とコストの理解が鍵です。
加入後の保障削減期間や免責の有無を事前確認し、用途に合う最小限の保障に絞りましょう。
引受基準緩和型保険の上手な使い方
告知項目が少なく、既往歴があっても加入しやすい反面、保険料は割高です。削減期間の有無を確認しましょう。
終身・定期の両系統で選べるため、目的に応じて小口でピンポイント加入がコツです。
無選択型保険の注意点
無告知で加入できますが、保険料と条件は重めです。上限額や免責、給付削減期間を要チェックです。
他の保障で代替できる部分は外し、必要最小限の金額設定にします。
タイプ別の特徴・メリット・注意点(早見表)
よく選ばれる三種の基本的な性格を押さえ、重複を避けてシンプル設計に近づけましょう。
表は方向性の比較で、個別商品の詳細はFPに確認するのが安全です。
| 特徴 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 終身保険 | 一生涯保障と貯蓄性 | 高齢加入は保険料が高い |
| 変額保険 | 資産形成と保障の両立 | 価格変動リスクと管理負荷 |
| 養老保険 | 満期で資金を受取 | 返戻率が低めで柔軟性乏しい |
実践プロセス:最小コストで不足だけを埋める
順番に点検すれば、過不足が自動的に見えてきます。やるべきことを工程化して迷いを減らしましょう。
以下の手順で洗い出し、保険の役割を「不足部分の補助」に限定します。
1. 年金・収支・貯蓄の棚卸し
毎月収支と金融資産の内訳を整理し、取り崩し許容量を確認します。キャッシュ等の流動性も把握します。
この時点で不足幅の概算を掴み、保険での補填規模を仮決めします。
2. 医療・介護の自己負担見積もり
高額療養費の上限、介護の自己負担上限、対象外費用を別建てで試算します。交通や差額室料は現金枠です。
自治体サービスも確認し、民間保険の上乗せ範囲を絞り込みます。
設計のコツ
対象外費用は保険で全額を狙わず、貯蓄と折半に。家計の月次負担を一定に保つと継続しやすくなります。
3. 死亡時費用と相続の整理
葬儀・整理費、未払費用、納税見込みを集計します。受取人や遺言の整備で家族の事務負担を下げます。
小口の終身や葬儀保険で即時資金を確保すると実務がスムーズです。
4. 既契約の重複チェック
医療・がん・共済の重複を洗い出し、費用対効果が低い特約を停止します。更新時の値上げにも注意です。
同等保障が複数ある場合は、解約返戻金や保険料総額を比較して最適化します。
見直しタイミング
更新・年金受給開始・介護認定などの節目で見直すと、保障と家計のミスマッチを素早く是正できます。
5. 必要最小限の保障設計
死亡は小口の終身、医療は一時金中心、介護は一時金+年金の併用など、役割分担で薄く広く備えます。
変額保険や積立で長期の資金づくりも併走し、取り崩し不安を軽減します。
FPに聞く!65歳からの保険と家計のリアル

制度と商品が多すぎて迷うとの声に、読者代表(34歳女性設定)がFPへ具体的に質問しました。
34歳・女性
傷病手当金がない自営業の親に、就業不能の備えは必要ですか?
スマホdeほけん
入院・在宅療養で収入ゼロが続く前提なら必須です。まずは一時金を小口で持ち、足りない収入は就業不能保険で補完する設計が現実的です。
34歳・女性
高額療養費があるなら医療保険は最低限で良いですか?
スマホdeほけん
医療費は抑えられても差額ベッドや交通費は対象外です。家計の流動資金と相談し、短期入院に強い一時金を中心に最小構成で十分です。
34歳・女性
老後資金を減らさないために、変額保険は向いていますか?
スマホdeほけん
長期分散を前提に、保険料の一部を変額保険で積み立てるのは有効です。ボラティリティを理解し、受取開始時期から逆算して配分します。
34歳・女性
持病があっても入れる保険の選び方は?
スマホdeほけん
緩和型と無選択型を比較し、削減期間や免責の条件を確認します。高コストなので金額は必要最小限に抑えるのが鉄則です。
34歳・女性
保険と貯蓄のバランスはどう決めれば良いですか?
スマホdeほけん
保険は不足額の補助、貯蓄と年金で基礎を固めるのが原則です。固定費が家計を圧迫する場合は、保障をさらに絞り込んでください。
Q&A:65歳からの生命保険のよくある悩み

Q1. 70歳を過ぎても加入しやすい保険はありますか?
A. 緩和型や無選択型なら選択肢があります。保険料は割高のため、必要額を小さく設計し、既存の共済や貯蓄と組み合わせましょう。
告知条件や削減期間の有無を必ず確認してください。
Q2. 定期と終身、どちらが良いですか?
A. 葬儀費などの恒常ニーズには小口の終身、時限的な不足には定期が向きます。目的別に役割分担すると保険料効率が上がります。
更新で保険料が上がる点は定期の注意点です。
Q3. 医療保険とがん保険は重複しますか?
A. 入院や通院の給付が重なる場合があります。既契約を精査し、足りない部位だけ追加するのがムダのない選び方です。
初回一時金や通院特約の重複にも注意しましょう。
Q4. 共済と民間はどちらが良いですか?
A. 共済は割安でシンプル、民間は選択肢が豊富です。必要額が大きい場合や条件重視なら民間、小口なら共済の併用も有効です。
年齢上限や保障打切り時期は必ず確認してください。
Q5. 保険料が家計を圧迫します。どう減らせますか?
A. 役割が重複する特約を外し、死亡は小口、医療は一時金中心に圧縮します。不足だけを保険で埋めると総額が下がります。
浮いた分は生活防衛資金と長期積立に回しましょう。
まとめ:不足だけを賢く保険で補い、老後資金を減らさない
65歳以降は公的制度と年金を軸に、対象外費用と長期費用を保険で最小限に補う発想が重要です。
死亡は小口の終身、医療は一時金中心、介護は一時金+年金型で薄く広く備え、家計の固定費を抑えましょう。変額保険等で資産形成も並走させると安心です。
監修者からひとこと



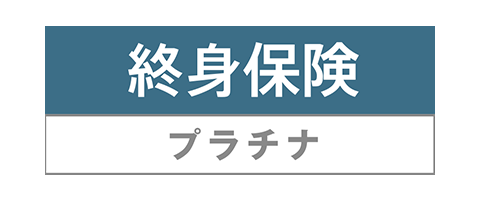
スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
高齢期の保険は「足し算」ではなく「引き算」の発想が要点です。まず年金と公的保障でどこまで賄えるかを可視化し、不足分だけを民間保険で補完すれば、保険料の上振れを抑えられます。更新や特約の重複を放置すると、家計の固定費がじわりと膨らみます。
設計は、死亡は小口の終身、医療は短期一時金、介護は一時金+年金の併用が基礎形です。資産取り崩しを避けたい方は、積立や変額保険の活用も検討しましょう。個別条件で最適解は変わるため、定期的な見直しと専門家の伴走を推奨します。