

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
保有資格
AFP・2級FP技能士
専門分野・得意分野
生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。
「就業不能保険はやめたほうがいいのでは?」
そんな疑問を抱えている方は少なくありません。
確かに、病気やケガで仕事を休むリスクに備える就業不能保険は魅力的に見えますが、本当に必要な人と、そうでない人がはっきり分かれる保険です。
この記事では、就業不能保険が「やめたほうがいい」とされる理由、加入の判断基準、必要な人の特徴、さらに保険以外の具体的な備え方についても解説します。
制度の仕組みからデメリット、見落としやすい注意点まで、初めての方でもわかるよう丁寧に説明していきます。
1. 就業不能保険とは?概要と基本の仕組み
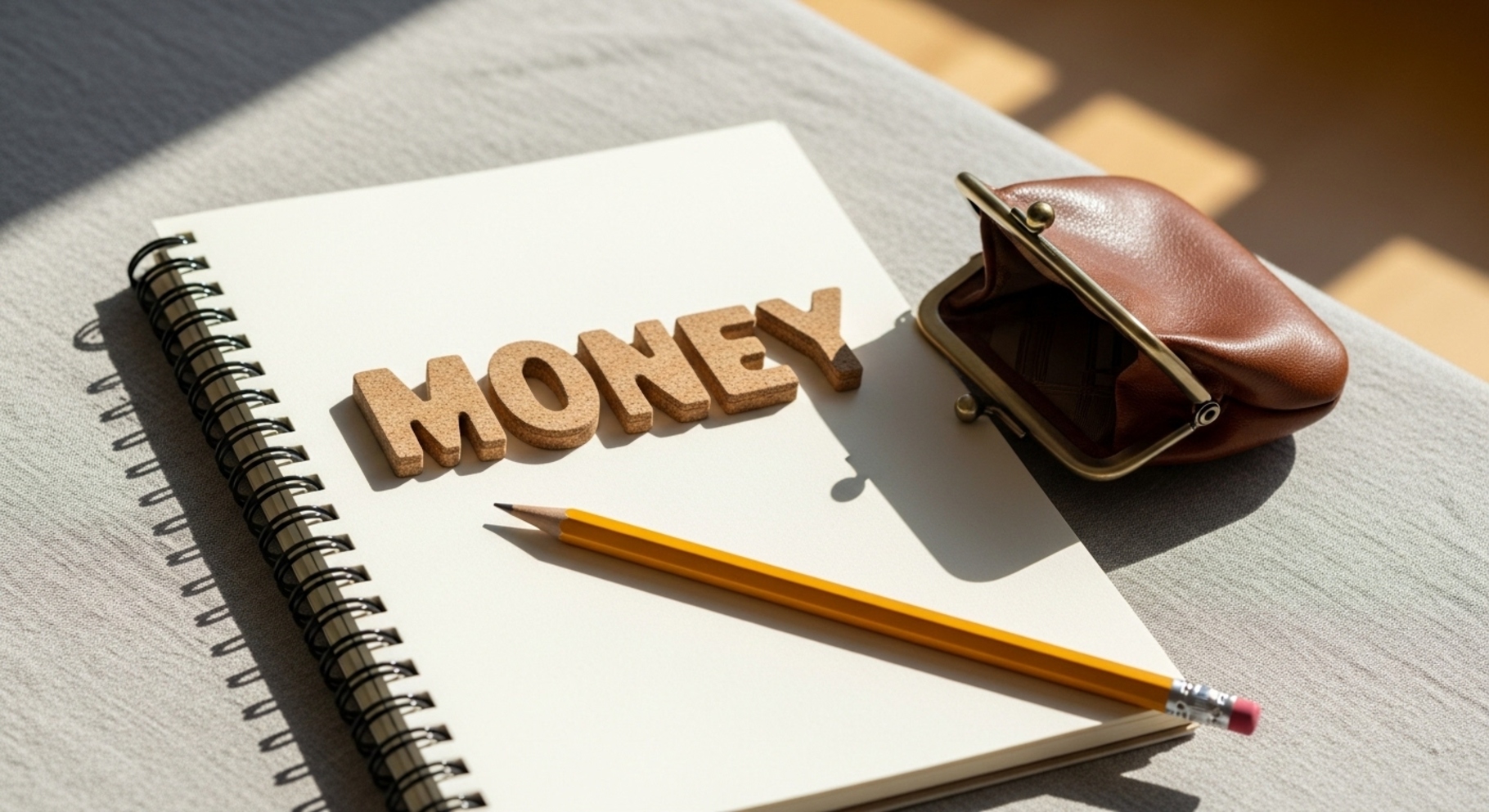
就業不能保険とは、病気やケガで働けなくなった際に、収入減少に備えるための保険です。
「長期療養で収入が絶たれたときに、生活費を補う」ことを目的として設計されています。
支給形態には、以下のような種類があります:
| 給付タイプ | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 毎月給付型 | 就業不能状態が続く間、毎月決まった金額が支払われる | 免責期間終了後の継続給付条件に注意 |
| 一時金型 | 一定期間の就業不能後、まとめて給付される | 再発時の対応や複数回給付の可否を確認 |
ただし、保障を受けるには保険会社ごとの所定の条件を満たす必要があり、「思っていたより給付対象にならなかった」と感じることも多いです。
2. 「就業不能保険はやめたほうがいい」と言われる5つの理由

就業不能保険をやめたほうがいい主な理由
1. 免責期間が長くすぐに給付されない
ほとんどの就業不能保険には「免責期間」が存在します。これは保険金が支給されるまでの待機期間のことで、60日・90日・180日などさまざまです。
たとえばうつ病で90日休職して復職した場合、免責期間が180日なら保険金は1円も支給されません。
多くの人が想定している「少し長く休んだら保障される」というイメージとは、実態が大きくかけ離れています。
2. 精神疾患の保障範囲が限定的
現代ではうつ病や不安障害など、メンタル疾患による休職者が増えています。
しかし就業不能保険では、精神疾患を支給対象外としている商品が多いのが実情です。
保障されるとしても「60日以上の入院」などの厳しい条件が設けられており、通院や在宅療養のみでは給付されないケースがほとんどです。
3. 公的保障がある程度カバーしてくれる
会社員や公務員であれば、以下のような公的保障制度により、ある程度の収入減少は補うことができます:
| 制度名 | 内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| 傷病手当金 | 給与の約3分の2を最大1年6ヶ月間支給 | 健康保険加入の会社員、公務員 |
| 障害年金 | 障害の程度に応じて毎月支給 | 国民年金または厚生年金加入者 |
民間保険に頼らずとも、一定の生活は維持できるという方も多くいます。
4. 給付条件が複雑で誤解されやすい
就業不能状態の定義は保険会社ごとに異なり、「医師の指示による療養」「入院継続」「一定の障害等級」など細かな条件が設定されています。
加入時に「大丈夫だろう」と思っていても、実際に働けなくなったときに給付対象外になる例も少なくありません。
5. 保険料に対する費用対効果が低い
月々2,000〜5,000円の保険料を数十年支払っても、一度も使わなければすべてが無駄になります。
就業不能保険は、使う機会が限られているため、「損をする人」が圧倒的に多い保険であると言えます。
3. 就業不能保険が不要な人の特徴
生活費を自己資金でカバーできる人
6ヶ月~1年分の生活費を預貯金で確保している場合、収入が止まってもすぐに困ることはありません。
公的制度が整った会社員や公務員
傷病手当金や有給休暇などが活用できる環境にある人は、短期的な就業不能なら民間保険なしでも乗り切れるケースが多いです。
扶養のない単身者
自分一人の生活費であれば、少しの貯蓄でカバーできることもあり、保険の必要性は下がります。
4. 就業不能保険が必要になる人の特徴
フリーランス・個人事業主
傷病手当金などの制度がなく、働けなくなると即「収入ゼロ」に陥るリスクがあります。
貯蓄が少ない場合は、就業不能保険でカバーする意義が大きくなります。
子育て中で一家の大黒柱である人
収入が途絶えると家族全体の生活に影響が出るため、保険によるサポートが安心材料となることがあります。
長期ローン返済中の方
住宅ローンや教育ローンなどを抱えている場合、返済中に収入がなくなると生活が一気に苦しくなります。
5. 保険以外にできる3つの備え方
1. 生活防衛資金を貯めておく
まずは最低でも6ヶ月、できれば12ヶ月分の生活費を現金で準備しておきましょう。これが最もシンプルかつ確実な備え方です。
2. 医療保険・がん保険で医療費対策
医療費に関しては医療保険、がん保険で備え、生活費については貯蓄でカバーするという分担方式が効率的です。
3. 固定費の見直しによるリスク耐性アップ
日々の支出を抑えることで、万が一の時に生活を維持しやすくなります。家計改善も立派な「保険」です。
6. 引受緩和型と通常型の違いとは?
| タイプ | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 引受緩和型保険 | 持病や通院歴があっても加入しやすい | 保険料が高く、免責期間が長いことがある |
| 通常型保険 | 保険料が安く、保障が充実している | 健康状態に関する告知が厳格 |
7. まとめ|「不安だから入る」ではなく、必要性を冷静に見極めよう
就業不能保険は、すべての人に必要な保険ではありません。
貯蓄、公的保障、支出の見直しといった手段でも十分にカバーできる人が多く、保険料を払い続けるより効率的なこともあります。
一方で、自営業やフリーランスの方、子育て中の家庭など、社会保障の外にいる方にとっては、大きな安心材料となる可能性もあります。
「とりあえず不安だから」「勧められたから」という理由ではなく、自分の収支や家族状況をふまえて判断することが大切です。
監修者からひとこと




スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
就業不能保険は、すべての人にとって必要とは限らない保険です。
特に会社員や公務員の方は、傷病手当金や障害年金などの公的制度が整備されており、実際に長期間収入がゼロになるケースは限定的です。
一方で、自営業者やフリーランスなど、社会保障の恩恵を受けにくい立場の方は、働けないリスクに直面したときの備えが重要です。
保険に加入するかどうかは「不安の有無」ではなく「制度と家計を踏まえた必要性」で判断すべきです。
加入前に、保険会社の保障条件や免責期間、公的制度との違いを比較し、納得したうえで選択しましょう。